「認知症」を防ぎ、高齢になっても働き続けるために… 明確に“予防できる”認知症の種類とは?
聴力に関しては、4000㎐の高音域の聴力低下は騒音難聴と言われ、昔であれば工場での機械の音など、職場の騒音が原因となっていることも少なくありませんでした。
現在ではヘッドホン、イヤホンを着けて大きな音量で音楽を聴くと、工場での騒音などと同様に、騒音難聴を起こすことが知られています。
難聴はそれだけでも日常生活が不便になるものです。
しかし、難聴を予防する必要があるさらに大きな要因は、難聴は認知症の発症率を約2倍増加させることです。
ランセットという、医学会で権威のある雑誌で発表された論文では、認知症の危険因子がいくつか挙げられていますが、「過度のアルコール消費」や「喫煙」「うつ病」とともに「難聴」が挙げられています。
そして認知症における難聴の危険度は、高LDLコレステロールと並んで関連性が最も高いとされています。
難聴になると、会話やコミュニケーションが困難になり、社会活動への参加が減少し、孤立するリスクが高まります。孤立や社会的なつながりの欠如は、認知機能の低下を招く要因です。
また難聴により聴覚からの情報入力が減少すると、脳の聴覚野を含む特定の領域の活動が低下します。すると、脳のネットワーク全体の活動の減少につながり、認知機能が低下する可能性が高まります。
難聴につながらない音楽の聴き方
それでは、難聴につながらないような形で、好きな音楽を楽しんで聴く方法はないのでしょうか。
WHO(世界保健機関)は、難聴を予防する安全な聴き方として、ヘッドホンやイヤホンを着け、80㏈(走行中の電車内くらいの音量)で、1日5時間程度までの使用を推奨しています。
人によっては「時間が足りない!」と思うかもしれません。その場合は、ノイズキャンセリング機能を使って、音量を下げるようにしましょう。
ビジネスパーソンとして、また引退後の生活の質を保つためにも、音楽の聴き方に気をつけましょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




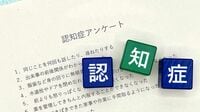



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら