「認知症」を防ぎ、高齢になっても働き続けるために… 明確に“予防できる”認知症の種類とは?
前頭葉は感情の制御や自己抑制に関する部位であり、帯状回は感情や注意力の調整に関与する部位です。
60歳を超えて働くうえで最も大切なのは、周囲と円滑にコミュニケーションが取れるかどうか、つまり一緒に働きやすい人でいることです。
なぜならば、周囲の人は年上の人に対して敬意を持って接し、会社の先輩として立てる意識があるため、業務上で意見が違っても率直に伝えづらい、といった現実があるからです。
その時に「あの人はすぐに怒るから、あまり意見を言わないでおこう」と思われるのか、「コミュニケーションが円滑に取れる人だから、相談ができてこちらも助かるな」と思われるのかによって、本人も周囲も気持ちよく働けるかどうかが決まります。
円滑なコミュニケーションを取ることは、長く働くうえで重要な要素の一つです。そして、それを支えるのが健康な脳機能です。
アルツハイマー型認知症や血管性認知症を予防することで、認知機能を維持し、周囲から「一緒に働きたい」と思ってもらえて、健康に働き続けることを目指しましょう。
血管性認知症は予防可能。生活習慣の改善により脳の血管を守り、将来も一緒に働きたいと思われる人材でいよう。
「難聴」は認知症の危険因子のひとつ
好きなミュージシャン、推しが歌う楽曲は何度聴いてもいいものですよね。聴けば聴くほど心地よくなってきますし、ライブでその曲が少しアレンジされて演奏されると、心が湧き立つ思いで興奮度が上がっていきます。
通勤時間や仕事中、場合によっては余暇の時間のほとんどを、ヘッドホンを装着して過ごしている人もいるでしょう。
ここでは、音楽を長く楽しむために、ヘッドホンやイヤホンでの音楽鑑賞で気をつける点をお伝えします。
健康診断の聴力検査の結果でまず注意すべきなのは、前年から大きく変化していないかどうかです。聴力に変化があれば、それに関わる病気の可能性があるからです。
また年齢とともに、高音域の聴力低下が発生する変化もあります。



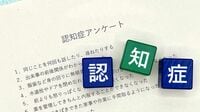



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら