「認知症」を防ぎ、高齢になっても働き続けるために… 明確に“予防できる”認知症の種類とは?
つまり現時点では、アルツハイマー型認知症については、まだまだわかっていないことが多いのです。
そのため、予防に関しても、脳血管疾患の予防と同様に、生活習慣に気をつけることが主な対策として推奨されています。具体的には、健康的な食生活、定期的な運動、社会的なつながりを持つ、頭を使う活動、生活習慣病の管理などが勧められています。
明確に予防できる認知症の種類
しかし、認知症の中で明確に予防できるものがあります。それは血管性認知症です。
血管性認知症とは、脳卒中や脳の血流障害が原因で発生する認知症です。
血管性認知症は、認知症患者の15〜20%を占めると言われています。
脳内の小さな血管の損傷も発症に関与しており、画像検査ではわからない程度の血管の詰まりや破れも影響しています(小さな血管の損傷については後述します)。血管の詰まりや破れなどの現象が起こると認知症の症状が急に悪くなり、しばらく経つと症状が変化せず安定する、悪化と安定の時期を繰り返します。
そのため血管性認知症の症状は、段階的(急に悪くなる時期と安定している時期を繰り返す)に進行することが特徴です。
大きな脳卒中後は、小さな血管の詰まりの場合よりも、さらに急激に認知機能が低下します。
その後の経過は、安定期(新たな血管障害が発生せず認知機能が一定の状態を維持している期間)と低下期(新たな脳梗塞や脳出血を起こし、特定の認知機能の低下が目に見える形で現れる期間)を繰り返すことが多いです。
血管の詰まりや破れの部位により、発生する症状に違いがあります。注意力・集中力の低下、実行機能障害(計画を立てたり、物事を順序よく進めることが難しくなる)、感情の変化(抑うつ、不安、攻撃性や怒りなど)など、さまざまな症状が起こります。
認知症の中でも血管性認知症は、生活習慣の改善により予防できます。



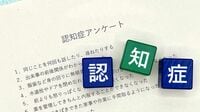



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら