なぜ「クレヨンしんちゃん」はアジアで愛されるのか? 不朽のキャラクターを生んだ臼井儀人という作家の魅力
特にこの地域別の中で、チャンスと明確に言える国は中国だろう。ウルトラマンにNARUTO、コナンにポケモン、ドラえもんと近年子供向け市場として日本IPの中国展開はすさまじい成果を上げている。
この他にも「おしりたんてい」や「おまえ うまそうだな」といった絵本ジャンルのポプラ社は中国絵本市場で2~3割といったシェアに成長している。すでに半世紀以上も子供向けジャンルを開拓してきた日本IP、特にここ30年かけて長編アニメのアーカイブを形成してきたクレしんのようなIPは、中国における人気次第で日本の倍以上もの市場規模で再興する可能性を持っている。
すでに円谷プロダクションが「ウルトラマン」で100億円超の売り上げとなり、その半分以上を中国からのライセンスだけで稼ぐようになったこの数年のトレンドを踏まえても、双葉社にとっての大きな商機が眠っている国であることは確かである。
ドラえもん・コナン・クレしんの共通点
そもそもなぜ日本で、そして海外まで、このキャラクターが届いたのだろうか。毎年の映画興行はドラえもん(1980年~)、コナン(1997年~)もそうだが、クレヨンしんちゃん(1993年~)もずっと続いている。
ドラゴンボール(1986~1996年)も、ONE PIECE(2000~2009年)も実現しえなかった「毎年恒例の家族映画」の枠に、この3キャラクターだけが残り続けているのだ。
これは家族と行ける二世代映画かどうかも重要であるし、ドラえもんのような昭和家族から自立して「外に向かう」子供像ではなく、友達関係のような平成家族で冒険の末に家族の絆を見つける「内に向かう」子供像という意味で、時代を象徴したものであったと捉えることもできる。そしてちょっと背伸びした下ネタや親の関心事のマネゴトをするしんのすけの姿は、テレビメディアで早熟に育った平成の子供たちと共鳴していた。少なくともサザエさんやドラえもん以上に、「家族」についてよく考える映画と言えばクレしんだった。
最後にクレしんの経済圏についてまとめたい。1992年のテレビアニメで書籍が売れ、1993~1994年は劇場版にゲームにCDにと、さまざまな商品化が派生していくが、これまでのキャラクターがそうであったように3年もたたずにブームは消失していく。













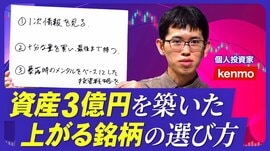


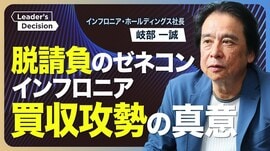




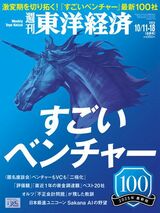









無料会員登録はこちら
ログインはこちら