営業なのに「電話が怖い…」、若者に広がる「電話恐怖症」のリアル。電話が苦手な部下に上司はどう対応すればいいのか?
一方、当時のような「効率」を目的にしたものではなく、昨今は「効果」に主眼を置いたシステムが注目を集めているのだ。その代表格が、電話の会話内容をAIによって分析するサービスだ。
・被せ率(被せる比率)
・ラリーの回数(話者が切り替わった回数)
・沈黙の回数
……などを定量的に測定し、アポ獲得や成約率向上につなげる。営業スキルを鍛えるうえでも効果的なシステムが、大企業を中心にかなり定着している。
つまり、電話が「苦手」「怖い」という若者(若者だけでないが)が増えている一方、プロのテレフォンアポインターのようなスキルを持つ営業パーソンもまた増えているのだ。
このように、高度なシステムと専門トレーニングでスキルを高めている営業がいる。しかし、そこまで時間と労力をかけられない企業はどうするのか?
そこで現在、活況なのが「電話代行」の業界だ。20年以上、営業コンサルティングの仕事をしてきたが、まさかここまで電話代行のビジネスが広がるとは、想像しなかった。
皮肉なことに、こうした電話代行サービスを支えているのは、主に20代から30代前半の若者たち。
私は、彼ら彼女らが主催する交流会にたびたび参加するが、誤解を恐れずに書くと、大学のサークルのようなノリで、若者たちは楽しんで仕事をしているように見える。SNS等で交流してインタビューするのだが「やりがい」がすごくある、と口を揃える。
「電話が怖い」という若者もいれば、電話代行のプロとして活躍する若者たちもいる。ある電話営業代行会社の代表は「弊社のオペレーターは9割が20代。彼らは驚くほど電話営業が上手い」と語る。
「電話が怖い」に対する誤解
先述した通り、日ごろから電話でコミュニケーションをとっていない若者なら、社会に出たあと電話に苦手意識を持つというのはわかる。それは、日ごろから運転しない人が車でお客様を訪問しろと言われているのと同じだ。
上司から何らかの「企画書」を作ってくれ、と言われても、スライドやドキュメントの資料を作った経験がほとんどなければ「できればやりたくない」「誰か他の人がやってくれないか」と思うのは自然な感情だろう。
しかし、社会に出たら「不慣れなこと」しか直面しないのも、また事実である。だから経験を通して慣れたらいいのだ。ただ、そのときに上司は注意すべきことがある。
それは、「とりあえず、自分なりにやってみろ」と丸投げしないことだ。たとえ自分が若いころ、そのように上司に指示されていたとしても、である。営業代行業の社長いわく「環境を整え、スキルを磨けば、まったく問題ない」そうだ。
「店舗で接客するのと、それほど変わりません。慣れない人は苦手意識を持つでしょう。だけど、専門スタッフと一緒にトレーニングを重ねれば、みんな上手になりますよ」














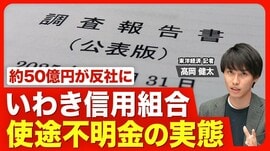

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら