ラーメン業界はここ数年、人件費、電気代、原材料費の高騰に加え、1000円以上の価格設定が敬遠される「1000円の壁」問題で、倒産が相次いでいる。そんな逆風の中での急成長である。
しかし、神座もここまでずっと順調だったわけではないそうだ。特にコロナ禍の2020年は、売上高が前年71億円から49億円まで急降下している。

V字回復の転機となったのは、2021年4月に行われた、創業者 布施正人氏から次男 真之介氏への事業承継だった。真之介氏は、高校卒業後にアメリカの大学に進学。2001年の「9.11テロ」を受けて帰国し、慶應義塾大学を卒業後、投資信託会社を経て理想実業に転職。その後独立して投資会社を設立した経験を持つ。
この経験を活かして中長期の経営戦略の見直しを図り、「10年後、700店舗展開」の構想を掲げたのだ。
「例えるなら創業者は、器のなかを中心にした美学を持つ職人です。いかにおいしいもの、うつくしいものを提供するかを第一に考えていました。
一方、2代目社長はアナリストとして上場企業の経営陣にヒアリングする立場にいたため、職人的な『器の美学』を大切にしつつ、『知識とデータをお客様第一主義』に落とし込んでいったのです」
コーポレートブランディング部課長で広報を担当する大林大輔氏はそう説明する。
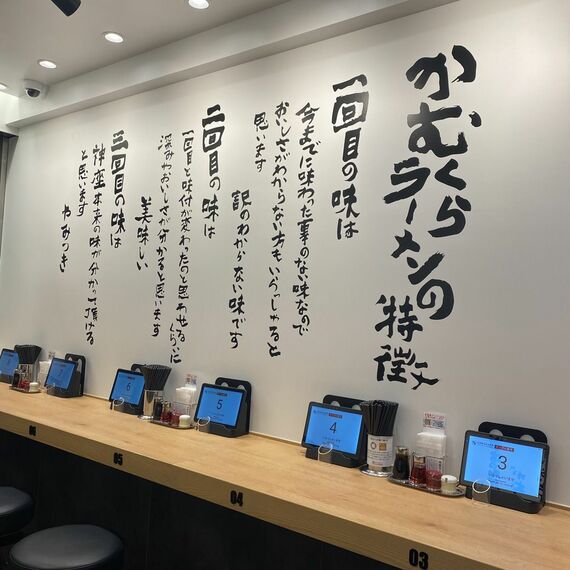
ただし、真之介氏の社長就任については、「コロナ禍で業績が悪化したことを受けて、創業者の妻である維久子氏、長男の直人氏と共に、真之介氏が創業者を解任したクーデターだ」と指摘する声もある。
双方で見解が分かれるところだが、承継後に真之介氏は700店舗の目標に基づき、出店時期とエリア、出店数までを綿密に試算。今日まで、戦略的な資本投下を進めてきた。その結果、売上高と店舗数が一気に成長、若い女性客を含め、幅広い客層の獲得に成功したのだ。
立地戦略が新規客層の開拓に奏功
なぜ、客層に変化が起きたのか。その最大の理由は立地の転換だ。従来、神座は「酒のあとの〆として重宝されるラーメン店」という位置づけで、飲み屋街やオフィス街の近隣に出店してきた。
















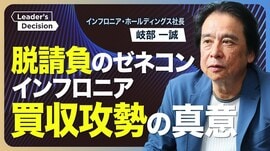




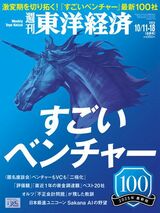









無料会員登録はこちら
ログインはこちら