「相場の30~40%でも売れない」管理組合理事の“独裁”で悪評吹き荒れた渋谷一等地マンションの住民が受けた理不尽な支配(後編)
世間の風潮に鑑みても、とても開催に踏み切ることはできなかった。住民の中には仕事を失う可能性がある人、生活に不安を抱える人もいた。賛同者に高齢者が多いことから、集会によるクラスターの発生を恐れた面もある。有志の会や自治会と日常生活を天秤にかけた時、大半の住民が自分の生活を優先した。手島にはそのことを咎めることなどできなかった。
そんな中でも月に1度のメルマガ配信だけは継続した。ようやく有志の会の活動が再開したのは、4カ月後、7月24日の昼下がりであった。通常であれば固定メンバーが10名ほどは参加していたが、この日は手島、今井、桜井の古参の3名の参加に留まった。
「前年のことが噓のように、委任状の数(の増加)も止まってしまった。それどころか、賛同者から抜けていく人もどんどん出てきたのです。集会すらままならないのですから、仕方ないですが、ゴールが見えない絶望感があった。ただ、私が折れると本当に終わってしまうかもしれない。病の身でも何とか顔に出さないように振る舞っていました」
マスコミの取材に対して心配も
そんな折に私は佐藤と出会った。後に聞いた話だが、マスコミの取材が入ることに対して慎重な意見も少なくなかったという。
「取材により秀和幡ヶ谷が荒らされるのではないか」「自分たちの生活に弊害が生まれるのではないか」こんな声が上がった。おそらく私が区分所有者でも同じように感じただろう。
これまで配慮に欠けたマスコミ取材が原因で活動が崩壊してきた現場を数々見てきた。マスコミを警戒する彼らの感覚は概ね正しい。むしろ、その慎重さゆえにここまで活動が成り立ってきたのだろうと想像がついた。
行政や警察、司法も議員も動けない。そんな中で、藁にも縋るような気持ちでイチ記者である私に、人を介して佐藤からのコンタクトが届いた。
「正直に言うと、今後どうしていいのかもう分からなかった。理事会に委任状を預けている人たちは、有志の会の言動を『妄想だ』と捉えているような節すらあった。理事会がそう吹聴していたから、そのまま信じていたんだと思います。加えて、理事会のルールなど管理状況を一切知らなかった、知ろうとしなかった人たちも一定数いた。その見解を崩すには、我々の活動だけでは限界が来つつあった。もしかしたら一つの報道が流れを変えるかもしれない。そう信じるしか他に選択肢がなかったんです」



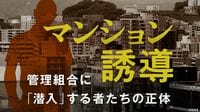



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら