食材卸で急成長「宝HD」がぶつかった"3つの壁" 日本酒を売る会社から日本食を売る会社へ

海外展開の中で宝が直面した“3つの壁”

前編では、同社が日本酒を広めるために、日本食を広げる取り組みをしてきたことをご紹介した。
とは言え、海外での日本食材卸事業には障壁もあった。本稿では、主なもの3つを紹介したい。
(1)国による、食品規制の違いの壁
障壁の中で、最たるものは食品規制の国による違いだ。
とりわけ欧州は厳しく、「ヨーロッパの規制がクリアできれば、アジアや北米にも適合できるケースが多い」と言われる。特に動物性の加工食品は乳製品も含めて規制が厳しく、なかでも、畜産由来のエキスを含む加工食品はほとんど輸出できない。
人気商品「とんこつラーメンスープ」にも畜産由来のエキスが含まれるため、ヨーロッパの基準に準拠した、現地工場で生産したものを仕入れているそうだ。また一部の商品にはEUのHACCP認証を持った工場からでないと出荷できない制約もある。
他方、農産物や、農産物を使用した食品にも別の課題がある。ヨーロッパは、消費者に渡るまでの製品のルートを明示する「トレーサビリティ」に厳格だ。だが、日本では農家レベルまで追跡確認するのは容易ではない。残留農薬量についても、日本製品は「有機JAS規格」など、堆肥や栽培方法などの厳しい規制をクリアした証明があるものしか、ほぼ輸出できないという。
食品添加物の規制も国によって大きく異なる。日本では約800種以上が認められているが、ヨーロッパでは約300種類しか認められていない。2025年1月には、アルミのパウチやプラスチック容器、缶のコーティング材として使用される場合がある「ビスフェノールA(BPA)」が、発がん性や生殖毒性の疑いがあるということから、使用した食品接触材料及び製品の流通がEU全体で禁止された。
このように、規制や法律は政治的な影響もあって刻々と変化する。「できるだけ早く正確な情報を掴み、変化に合わせていく必要があります」と森社長は厳しい表情を浮かべる。
しかしその情報把握においては、各国にある連結子会社が持つ現地ネットワークが大きな強みとなっている。子会社には規制クリアのノウハウもあり、日本の商社とも協力しながら対策を講じているそうだ。
この規制問題の解決策の1つが、現地での食材調達だ。しかしこれは同社が直面した、2つめの壁でもあった。

(2)調達ルートや、物流網の壁
2つめの壁は、調達ルートや物流網だ。意外なことに、現在宝が取り扱う日本食材のうち、多くは現地で調達しているという。
コロナ禍には、国家間の物流が突然停止したり、再開後もコンテナ不足に悩まされたりと、国際物流の混乱が起きた。そのため同社は、パンデミックや紛争などによる社会的分断や物流リスクを回避するため、調達ルートの見直しに着手。マーケットに近い域内での食材調達を強化していったのだ。水産物も、ヨーロッパや東南アジアの養殖ものが増えている。

また同時期、取引のある日本企業が海外進出し、日本と同品質の製品を現地で生産するケースも増えた。そうなると、「現地の規制に適合した状態で供給してもらえる」という恩恵があるそうだ。
他方で、品質面で日本産の優位性が明らかなものは日本から調達している。脂の乗ったブリ(欧米ではハマチと呼ばれる)は代表格で、宮崎や鹿児島、四国から養殖ものを仕入れる。
そのような魚介類などを宝の連結子会社で、アメリカの日本食材卸会社であるミューチャルトレーディングでは、マイナス60度の「超冷凍」技術を駆使して全米へ届けている。この温度帯ではエキスが出ず、鮮度と品質を保ったままお客様へ届けることが可能だという。

(3)背景が異なる様々な子会社をまとめる上での「一体感の壁」
3つめは、子会社をまとめる上での「一体感の壁」だ。
グループ化によって連結子会社が急成長を遂げている一方で、多国籍に広がる連結子会社との関係構築は、グローバル企業の共通課題だ。宝は、文化や国民性の異なる海外企業をどのように統合し、グループの一体感を醸成していっているのか。
宝の解決策は、「グループに迎え入れる前から積み上げてきた各社の強みを活かす」スタンスを貫くことだった。グループ内のつながりで生まれる取り引き、仕入れのスケールメリット、「アメリカでこの酒が売れているから、ヨーロッパでも提案したら喜ばれるのでは」といった情報までを提供し、子会社の経営を支えているのだ。
経営に一切口出ししないわけではない。ガバナンスやコンプライアンス、環境方針などを浸透させるため、管理や会計などの担当者は宝から数名派遣している。

国民性の違いによる人間関係の難しさについては、「当然あるが、それは日本国内でも大なり小なりあるもの。ただし距離が離れているため、コミュニケーションの機会は積極的に作っています」と森社長は説明する。
海外スタッフを定期的に日本に招いて研修を実施したり、立ち飲み店や屋台、居酒屋などを巡って日本の食文化を体験してもらう取り組みも行っている。また、子会社のスタッフが顧客の同伴で訪れる際には、できるだけ京都にある社員研修施設「宝ホールディングス歴史記念館」や工場を見学してもらうという。

月1回以上のオンライン会議に加え、期初には、各社の社長が参加する全体方針会議も日本で開催。これらの努力の甲斐もあって、森社長が入社した1985年は従業員の大半は日本人だったが、今は海外で働く従業員の比率の方が高いそうだ。
今後はグローバルな情報網をさらに活かして、商品開発やサービス提案に積極的に取り入れていきたいと考えている。
「グループとしての一体感をどう高めていくかはまだまだ課題です。でも、酒造りの会社として創業し、酒造りの技術から、国内外のお客様へグローバルに届けられる流通ネットワークまで持っているのは、私たちの大きな強みだと感じています」
そして、なにより大切なのは、グループ全体を貫くビジョン「Smiles in Life」の共有だと強調した。
「日本食や日本酒を世界各地に紹介し、それを楽しむ場を提供することで、人に笑顔になってもらうこと。そのためのサービスをすることが私たちのベースです」
森社長自ら各地へ足を運び、そう、折に触れて伝えているそうだ。

3本立て最後となる後編ー澪が海外で大人気「宝酒造」驚きの日本酒革命 アメリカの酒蔵で「イノベーティブなSAKE」を開発ーでは、宝の海外での酒類製造・販売事業について詳しく解説していく。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




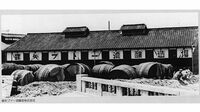


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら