「学校復帰」を目指す不登校支援はもう古い? N高人気にみる「学校に通わない」という選択肢。「不登校=年30日以上欠席」という前提を問い直す
学校の授業と相性の悪かった私にとって、インターネットを通じて出会った同じ趣味のプログラミング仲間には特別な絆を感じていました。Yahoo! メッセンジャーなどでしゃべったりしながら、互いにコードの書き方をオンラインコミュニティで夢中で学んでいきました。
17歳のときには、「はてなダイアリー」を書いているうちに仲良くなった熊本と三重に住む同世代2人とリモートで、Webサービス「ねみんぐ!」を開発しました。これは何でも画像をアップロードすると、名画風のそれっぽい名前をつけるオモシロサービスで、当時かなりバズりました。インターネット有名人たちが次々に取り上げてくれて、「すごくイイね」とみんなが言ってくれたのは、1つの成功体験になったと思います。
決して正統派の学びのルートではありませんでしたが、オリジナルなものをつくって世に受け入れられることの喜びを知ったのです。
特異な個性の持ち主たちがイノベーションを生み出す
こうした私自身の経験を踏まえても、脳の特性を理由に教育の既存のレールから外され、持っている力を社会に対して発揮できない状態になるよりも、すべての子の特性に応じた学びのパスがあって、創造性を発揮できる可能性が用意されたほうが、その子にとっても社会にとっても幸せなことだという強い思いがあります。
スタートアップ界隈を見渡せば、思考の特性に偏りがある個性的な面々が圧倒的なパフォーマンスを発揮していることが少なくありません。
イーロン・マスクは自らアスペルガー症候群だと明かしていますし、スティーブ・ジョブズはADHD、マーク・ザッカーバーグは自閉スペクトラム症といわれています。私が一緒に仕事をしてきた仲間たちの何割かもそんな一面を持っています。
特異な個性の持ち主たちも、才能を開花できるような環境が整えられることで、画期的なイノベーションを生み出しうるのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

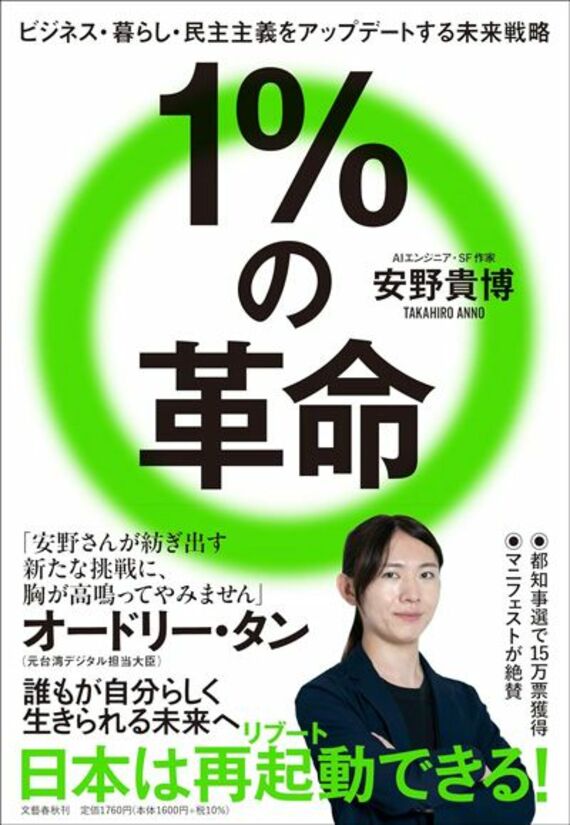
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら