ガイトナーの金融危機対応は正しかったのか リーマンショックの真相
両親の都合で幼少期をインドやタイで過ごしたガイトナーは、貧困国を生きる人々の現実とアメリカの影響力の大きさを実体験として思い知っていた。ビジネスでの成功よりも外交や国際開発に興味を持つようになった彼は、ヘンリー・キッシンジャーのコンサルティング会社でアジア担当アナリストとしてキャリアをスタートさせた。その後のガイトナーは、キッシンジャー以外にもラリー・サマーズやロバート・ルービンなどにその能力を認められ、経済学の博士号を持っていないにも関わらず、次々と出世の階段を登っていくこととなる。
キャリアの第一歩は日本だった
政策決定者になりたいと、公務員として財務省に移ったガイトナーは、29歳にして1990年に駐在財務官補という立場で日本にやってくる。日本こそが、ガイトナーが初めて金融危機を間近に見届けた場所であり、このときの体験はその後の彼の行動に大きな影響を与えている。アメリカの金融危機の結末として絶対に避けなければならないシナリオとして彼が思い描いていたのは、優柔不断な政策によってゾンビ銀行が生き延び、低成長にあえぐ日本の姿だったのだ。その後も、メキシコ、タイ、インドネシアなど、金融危機への対処していくなかでキャリアを築いていった。
信用というカタチのないものを相手にする金融危機では、何をするかよりもどう見られるかが重要となることも多い。ガイトナーも、本書中で繰り返し「金融政策という予想ゲームでは、内容よりも舞台の見栄えをよくするほうが大切だ」と強調する。
人前で話をするのが苦手だったガイトナーは、ある意味では危機の財務長官としての資質を欠いていたのかもしれないが、考え抜き行動し続けた彼の言葉には強度がある。「金融危機の最中に心配しないようなら、それは考えが足りない」、「懸念は戦略にはならないが、優れた戦略には欠かせない」など、危機を予測するのでも分析するのでもなく、対処し解決するヒントがあふれている。
ガイトナーが実施した金融危機対策は正しいものだったのか、いまだに議論は続いている。アメリカのGDPは危機前と比べて順調に成長しており、雇用も回復している。しかし、彼の危機対応とその後の改革が正しいものだったかが真に明らかになるのは、次の危機を迎えたときだろう。人々の信用という心理的要素が大きな役割を果たす金融危機においては、国民のリテラシー向上もその防波堤になりうる。危機の真実を伝え、次なる危機へ備えるための知恵を与えてくれる本書は、ガイトナーによる危機対応の総仕上げなのかもしれない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

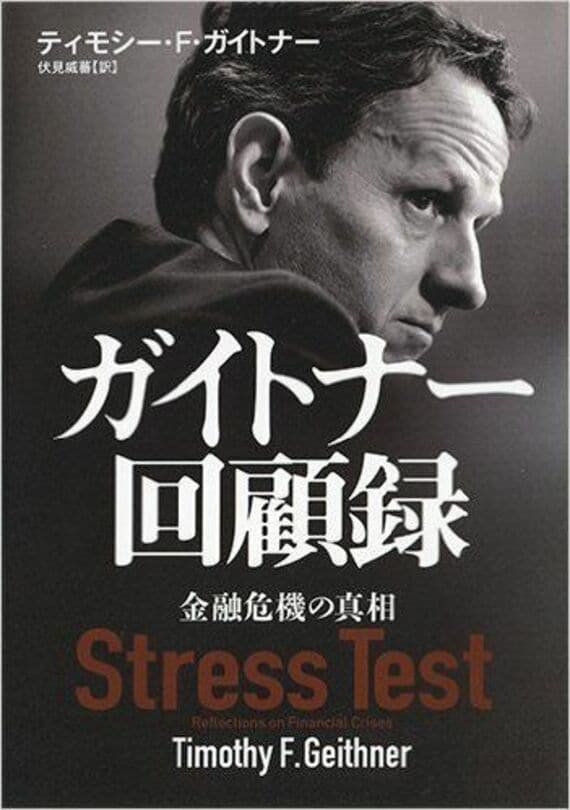






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら