事実上の人身売買「吉原遊女」たちの悲喜こもごも 妓楼でさまざまな「教養や所作」を学んでいった
花魁道中で履いた下駄は、元禄から宝暦期には三枚歯のものが流行していた。しかし、享和期には、江戸町一丁目の越前屋の遊女・和国が、三枚歯は古いとして、二枚歯を履き、やがてそれが定着したという。
遊女たちに求められた「幅広い教養」
さまざまな階層の客の相手をする遊女は、当然、その分、幅広い教養が求められた。特に大身の武士や豪商、文化人などの上客をとりこにするには、美貌だけでなく、それなりの教養が必要だった。
妓楼は抱えの遊女に教育を施し、教養を身につけさせることで、商品価値を高めようとした。禿には手習いをさせて読み書きを覚えさせた。
特に妓楼では、手紙が客との関係を保つ重要なコミュニケーションツールだったのである。
「けさ駕でかへりし客へほどもなく又かきおくるけいせいの文」という狂歌がある。今朝、駕籠で帰ったばかりの客に対して、傾城(遊女)から早速に手紙が届いたと詠んでいる。このような筆まめな活動によって、遊女はあの手この手で、客の心をつなぎとめようとした。
また読み書きだけでなく、遊女は書道、生け花、茶道、和歌や俳句、箏や三味線、囲碁・将棋といったさまざまな教養を身につけていた。吉原の外には出られないため、妓楼に師匠を招き、遊女は指導を受けた。
1754(宝暦4)年刊行の評判記『吉原出世鑑』には、遊女の嗜みとして、茶の湯や俳諧、琴、三味線などが記されている。
また、1756(宝暦6)年刊行の『当世武野俗談』には、松葉屋の遊女の四代目・瀬川は、三味線、浄瑠璃、茶の湯、俳諧、碁、双六、鞠、鼓、笛、諷詠、舞に秀でた多才な女性であったと記されている。さらに能書家で、絵は池大雅に就いたという。遊女たちの教養の高さがうかがえる。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら







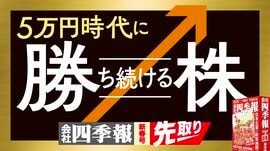







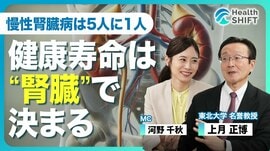
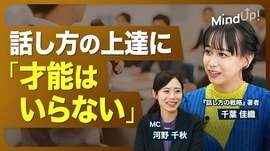






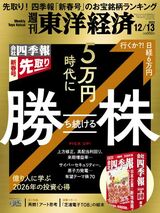









無料会員登録はこちら
ログインはこちら