事実上の人身売買「吉原遊女」たちの悲喜こもごも 妓楼でさまざまな「教養や所作」を学んでいった
午後6時頃(暮六ツ)から夜見世が始まる。再び張見世に並び、客がつくと、2階の座敷で酒宴が始まる。午前0時頃(引け四ツ)、妓楼の表戸は閉められ、新規の客はもう入れないが、登楼している客は、夜通し遊び続ける。
午前2時頃(八ツ)に大引けの拍子木が鳴らされ、遊女はいったん退出して、寝床の用意を整え、客とともに寝床へとつく。
その後も床のなかで、客の相手をして、夜が更ける。客は夜明け前に帰るか、そのまま居続けとなり翌日も一緒に過ごすこともある。
苦界と呼ばれた吉原での遊女の仕事は、毎日、複数の男性に身を売るなど過酷な労働であった。特に遊女を蝕んだのが病気、とりわけ性病であった。当時は性病を予防するコンドームもなく、性病の知識もない時代である。そのため、瞬く間に感染は拡大していった。
江戸時代に来日したシーボルトやポンペなどの外国人医師らは、日本人の間に梅毒や淋病が蔓延していることを指摘している。
日本人医師の橘南谿も『北窓瑣談』のなかで、「今にては遊女は、上品なるも、下品なるも、一統に皆黴毒なきは無く」と吉原(上品なる)・岡場所(下品なる)の違いなく、梅毒の蔓延を記している。
島国の日本は、流行病の多くは国外から持ち込まれることがしばしばである。梅毒がアジアに流入したのは、バスコ・ダ・ガマ一行が喜望峰を回りインド洋に入って、インドのマラバール海岸に降り立った1498年頃とされる。
これをきっかけに梅毒はインド全土に広がり、インドネシア、中国、琉球を経て、日本列島にも拡大していった。1510年代以降、ヨーロッパ人が日本に初めてきた頃より、梅毒が日本に到着したと思われる。
梅毒には感染初期に症状が出たのちに、長い潜伏期間があることで知られる。表面上は症状がおさまるので、快癒したと勘違いされた。梅毒にかかり寝込むことを「鳥屋につく」と言われ、そこから回復すれば2度と梅毒にはかからないと信じられた。しばしば鳥屋から回復して、一人前の遊女とも言われた。
一般女性も真似をした遊女の髪型
1617(元和3)年、吉原遊廓の設置許可に際して、幕府は五カ条の触書を出している。そのなかで、遊女の衣服の刺繍や金銀摺箔を用いた過度の装飾を禁じていた。






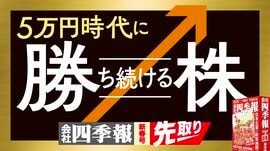







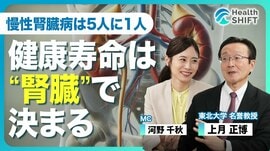
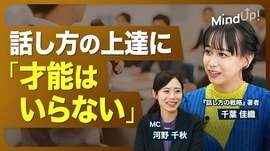






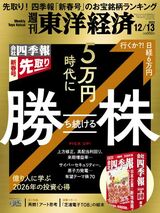









無料会員登録はこちら
ログインはこちら