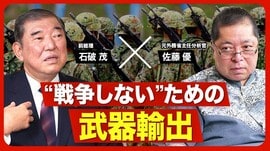五輪で注目"スケボー"施設、求められる「かたち」 設置自治体増加の背景、選手層の厚みを下支え
「老朽化した公園を改修するにあたり、自治体の担当者が『注目のスケートボードの施設を作るのはどうだろう』と、考えるわけです」
だが、自治体のスケートパークへの理解は「十分とはいえない」という。
「スケートパークは人や社会とのつながりを学ぶ『教育の場』であり、『自己発見の場』だとぼくは考えています」
今年1月、内閣府の「孤独・孤立対策に資するNPO法人等への調査」で、河崎さんらはスケートパークの企画・運営について、ヒアリングを受けた。
スケートパーク運営が「孤独・孤立対策や予防につながる」(調査報告書)とみられたからだ。
スケボーがコミュニケーションツール
「スケボーをしていると、周囲のスケーターから、『おお、うめえじゃん』とか『惜しい』とか、自然と声がかかる。
たとえば、ひきこもりだったり知的障害があったりしてうまく言葉が出なくても、スケボー自体がコミュニケーションツールだから、誰も気にしない。
でも、声をかけられたほうはうれしいから、またやってくる。いつの間にかコミュニケーションもとれるようになるんです」
スケボー仲間のコニュニティーは「安心できる居場所」であり、やがてそれは「人生のルーツ」になる。小学生のころからスケボーに「どっぷりはまってきた」河崎さんは、そう信じている。
「家庭がひとり親でも、勉強ができなくても、いじめられていても、スケボーの世界では関係ない。『スケボーだけは誰にも負けたくない。一生懸命にやってきた』という気持ちが人生の支えになるんです」
だが、スケートボードは難しい。自在に滑るためには、百回も千回も練習しなければならない。練習するには場所がいる。
もともとスケボーは、街なかの構造物を工夫して滑り、楽しむものだったこともあり、駅前の広場や階段、道路、公園などが練習場所になる。こうした公共の場でのスケボーの練習には、苦情が寄せられることも珍しくない。