はかりなき千尋(ちひろ)の底の海松(みる)ぶさの生ひゆくすゑはわれのみぞ見む
(途方もなく深い海底に生える海松──あなたの髪が伸びていく先は、私だけが見届けよう)
と光君が詠むと、
千尋ともいかでか知らむさだめなく満ち干(ひ)る潮(しほ)ののどけからぬに
(千尋の底の海松(みる)の行く末をひとりで見届けるとおっしゃいますけれど、本当でしょうか。今だって、満ち干る潮のように定めなく落ち着かないあなたですのに)
と姫君は手近の紙に書きつけている。そんな様子はずいぶんと大人びていながら、初々しくもかわいらしく、光君は満たされる思いがする。
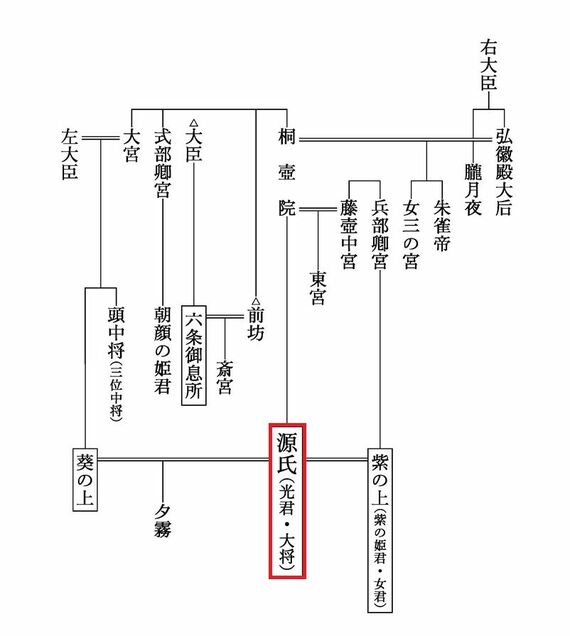
いったいどんな風流な女だろう
今日も、見物の車が隙間なく並んでいる。左近の馬場の殿舎のあたりで車の停め場所に困り、
「上達部(かんだちめ)たちの車が多くて、ずいぶんと騒がしいところだな」と停めるのを躊躇(ちゅうちょ)していると、派手に袖口を出した女車からすっと扇が差し出され、お供の者を手招きする。
「ここに車をお停めなさいませ。場所をお譲り申しますから」と女車の中から声がする。
いったいどんな風流な女だろうかと思いながら、確かにそこは見物にはいい場所だったので、光君は車を近づけた。
「いったいどうやってこんないい場所をお取りになったのか、うらやましいですね」と言うと、洒落(しゃれ)た扇の端を折り
「はかなしや人のかざせるあふひゆゑ神のゆるしのけふを待ちける
(つまらないことです、ほかの方が頭につけた葵──ほかの方のものになってしまったあなたなのに、そうとは知らずに、男女が逢うのを神さまも許してくださる今日の祭を待っていたとは)
注連縄(しめなわ)の内側にはとても入ることなどできません」
と書かれている。その筆跡を思い出してみれば、なんとあの源典侍(げんのないしのすけ)ではないか。年甲斐(としがい)もなく若ぶってあきれたものだ、と憎らしく思った光君は、
かざしける心ぞあだにおもほゆる八十氏人(やそうぢびと)になべてあふひを
(葵をかざして逢瀬(おうせ)を待っていたあなたの心はあてになりませんよ、だれ彼かまわずに今日は逢う日なのでしょうからね)
とそっけなく返した。典侍はなんてひどいことを、と傷つき、
くやしくもかざしけるかな名のみして人だのめなる草葉ばかりを
(お目にかかれるかと葵をかざしていたのがくやまれます、葵──逢う日なんて名ばかりの、虚(むな)しく期待させるだけの草葉にすぎないのですね)
と送った。





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら