「Google検索使いこなす子供」に潜む"大きな問題" 検索で出た答えは正しい?若者に必要な視点
「問いに対して、すぐに答えがほしい」「早く答えを出したい」という感覚があり、だからこそ1つの問いに対して粘る、ということがだんだん難しくなってきているのではないか、と。そうした状況は、大きな問題なのではないかと私は思うのです。
これは私の持論ですが、生きていくうえで「答えのない問い」に対して考える時間を持つのは、とても重要になってくると思います。「自分はどう生きるべきなのか」「どんな進路に進んでいくべきなのか」「幸せになるにはどうすればいいのか」。
生きていくうえで重要になってくる問いのほとんどには「答え」は存在しておらず、その「答え」を考えるまでに費やした時間が、自分の価値観として育っていくのではないでしょうか。
しかし、今の生徒たちはその「答えのない問い」に対して、粘って考えるという経験が少ない場合が多いです。この状態だと、人生の中で重要な選択をする際や、困難な状況に陥ったときに、「粘り強く考える」ことができなくなってしまうのではないかと思うのです。
倫理・哲学的な問いを考える時間を
それに対する解決策として、私は今の生徒たちには、倫理・哲学的な問いを考える時間を長く取ってほしいと考えています。
「安楽死は導入されるべきか」「死刑制度は継続されるべきか」「大学の女子枠は平等なのか」など、倫理・哲学で取り沙汰されるような問題というのは、「これ」という答えがありません。
素早く「こちらが正しい」と言えるようにするのではなく、賛成意見と反対意見を両方考えて、「答え」ではなく「よりベターな考えは、どちらだと言えるのか」を悩む必要があります。
実際に学生に体感してもらうと、その思考の速度の「緩さ」に困惑する人も多いです。しかし、慣れてくると、普段の問いに対しても、より深く答えを出そうとしてくれるようになります。速やかに答えが出せない問いを考えることで、タイパではない思考に対して耐性を付けることができるようになるのです。
タイパが当たり前とされる世の中だからこそ、すぐには答えのない倫理・哲学的な問いにじっくり向き合う時間も必要なのではないでしょうか。こうした問いに向き合う中で、生徒にとって不可欠な「容易に答えが出ないことに耐える力」が養われるのではないか、というのが私の考えです。情報処理の「速さ」に飲み込まれることなく、時には立ち止まって考える機会を持ってほしいと願っています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

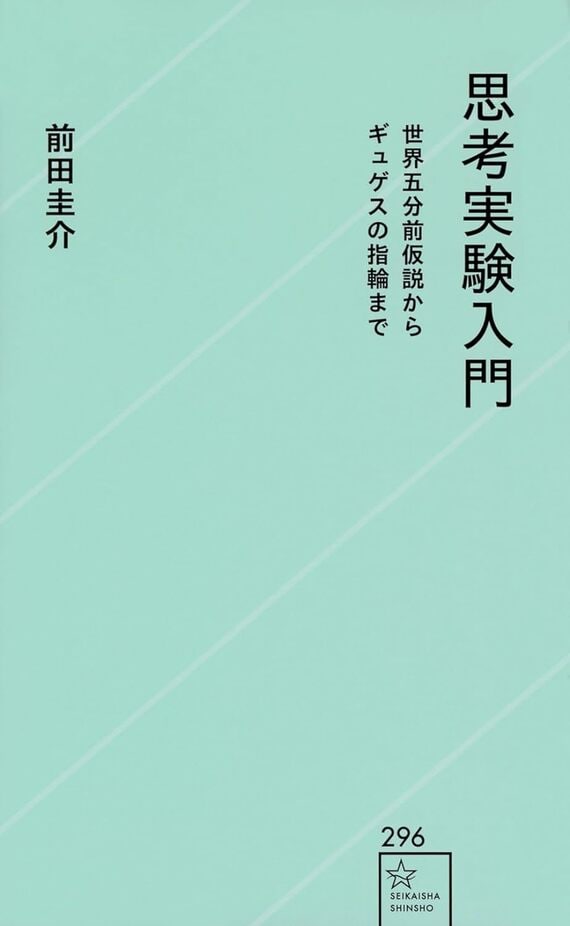































無料会員登録はこちら
ログインはこちら