なぜ若者は怒られると過剰に反応してしまうのか 上司にとって「怒らない=最適解」になる病理
ただまあ、ちょっと都合が良い。「メンタルにくるようなのは止めてほしい」「諭すように怒ってほしい」「頭ごなしに……」「感情的に……」。非常に細かい注文がつく。お金払ってるお客さんにだったら細かいニーズでも応えようとするのだけど、相手は部下だ。お金もらうんじゃなくて払っている相手だ。
一番選ばれやすい答えはきっと、こうだ。
「めんどくさいから怒らないで、放っておく」だ。
怒られない社会の病理
2023年の11月に元プロ野球選手のイチローさんが、高校生らに向けて話す動画が話題になった。北海道の旭川東高校野球部に招待され色々話をする中で、次のようにグラウンドで語りかける(書き起こし・句読点は著者加筆)。
「指導者がね、監督・コーチ、どこ行ってもそうなんだけど、厳しくできないって。厳しくできないんですよ。時代がそうなっちゃっているから。導いてくれる人がいないと、楽な方に行くでしょ。自分に甘えが出て、結局苦労するのは自分。厳しくできる人間と自分に甘い人間、どんどん差が出てくるよ。できるだけ自分を律して厳しくする」
いいことおっしゃる。本当に、現代にこそ必要な至言だ。大学でも職場でも、厳しくすることがほんとにできなくなっている。オトナは若者を怒らないし、怒れなくなっている。結果的に若者の機会を少なからず奪っているとすら思うけど、でもこの流れは止められない。それが「時代」なのだ。
時代って何なのか誰もよくわかってないけど、そうなっていったらもう抗えない、あまりに強い濁流。この令和の新しい時代に、若者はとても「むごい教育」を、残酷なことをされているのかもしれない。
怒られない社会・怒られない職場の病理は2つある。まず、若者の免疫があまりにも弱体化して、かえって怒(られ)ることを過大視しすぎてしまっていること。私語を注意するなんて何の気なしにされるようなことなのに、された方が人格否定のように、取り返しのつかない過ちを犯したかのように感じてしまう。
もう1つは、怒ることをネガティブに捉えすぎるがゆえに、もし若者が怒ってほしい・怒られるべきだと思っているときでさえも、上司は怒らないことを選択してしまうという問題である。それはもはや上司個人の問題ではなく、社会や組織の力学がもたらした「最適解」なのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




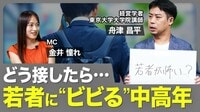


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら