渋谷TSUTAYAの大変貌は復活の序章かもしれない 「インフラを作る」企業ミッションの再定義だ
リニューアル前の渋谷TSUTAYAの大きな見どころが、館内にぎっしりと詰まった豊富なレンタルCD・DVD。中でも、VHSは他店では手に入らないマニアックなタイトルも揃えていて、多くの映画ファンに愛されている場所でもあった。
しかも、このことはTSUTAYA側も意識していたらしく、2020〜2021年時のリニューアルでは、「日本最大級の映画ミュージアム」と称して20万本の旧作を取り揃え、さらにVHSだけのコーナーを新設したのだ。それだけに、映画ファンからしてみると、このたびの再リニューアルは「ハシゴを外された!」と思ったに違いない。

また、「ヴィレッジヴァンガード」の業績不振が話題となり、ブックオフが「本」に限らない総合リサイクルストアへと変貌を遂げつつあるいま、「TSUTAYA」「ヴィレヴァン」「ブックオフ」という「平成カルチャーチェーン三銃士」の凋落を嘆く声も相まって、このリニューアルはどことなく悲観的に受け止められている。
同社のミッションはカルチュア・インフラを作ること
しかし、である。
私は、今回のリニューアル案を肯定的に語りたい。なぜ、私が今回のリニューアルを肯定的に捉えるのか、それは「TSUTAYAが『カルチュア・インフラ』という、創業からの企業理念を明確に意識している」と思ったからだ。
どういうことか、TSUTAYAの歴史を探りながら解説したい。
もともとTSUTAYAは、創業者の増田宗昭が大阪・枚方に作った店が始まりである。1980年代に誕生したこの店は、本だけではなく、CDやDVDなども同時に扱い、まさに「カルチャー」をその商材とした。当時、ジャンルを越境してコンテンツを扱う店は少なく、1号店は大きな評判を博す。
創業者である増田宗昭は、その著書のなかで、繰り返し「CCCの存在意義は『カルチュア・インフラ』を作ることである」と述べている。ガスや水道と同じように、文化を地方・郊外まで全国に広げていくことがその存在意義だというわけだ。




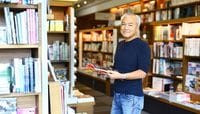


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら