国内の結核患者「外国出生者の割合増」が示す意味 2021年に「低蔓延国」になった日本、新規は1万人
「グローバリゼーションの時代には、人やモノの往来によって海外で広がっている感染症が、いつ日本に来てもおかしくない」と話すのは、22年から公益財団法人結核予防会理事長を務める尾身茂医師だ。
その上で、「世界が結核をある程度制圧しないことには、日本でも常に感染拡大のリスクがあると思ってほしい。日本では“結核は既になくなった病気”という認識を改める必要がある」と指摘する。
実際、結核の感染対策が功を奏したニューヨークでも、その対策を緩めた後、再び感染者が増加した。
外国出生者の患者の割合が増加
日本は低蔓延国になったとはいえ、2022年に登録された新規の結核患者は1万人を超える。とりわけ、近年注目されるのが、外国出生者の患者の割合が増えている点だ。
インバウンドがもたらす恩恵を考えるまでもなく、グローバリゼーションの波は否応にも押し寄せる。大切なのはいかに人の流れを止めるかではなく、ともに乗り越えるかの視点だろう。

「結核は、どこでも誰でもかかる可能性がある病気」だからこそ、結核予防会含め、日本が取り組んでいることがある。
その1つが、外国出生者が母国を出国する前に行うスクリーニング検査だ。検査で結核にかかっていないかを調べ、仮に見つかったなら、治療をしてから来日してもらう。
ただ結核は、後述するが感染から発症までの潜伏期間が長い。国を出るときは発病してなくても、日本に来て発病することは十分に考えられる。
その際には、「すぐに帰国してくださいだなんて言わないで、日本でしっかりと必要な治療を提供する。治療や予防に実績のある日本だからこそ、世界の中で果たせる役割がある」と尾身医師。
結核の怖さは尾身医師の言葉を借りるなら、「人に警戒心を与えない」だろう。そこが、感染すればもれなく発症して死に至るエボラ出血熱のような感染症と異なる。

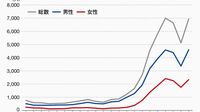
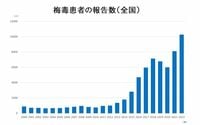




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら