陰謀論については、メディアリテラシー対策が叫ばれて久しいが、このような経験などを踏まえると、批判的思考を身に付けるだけでは限界がある。筆者は、真偽不明であることを知りながら、それでも「代替現実」のほうに惹かれたし、熱中した。まさに、ファン・プロイエンが述べたように「壮大な物語の能動的なプレーヤーに変え、素人探偵のように謎を解き明かす機会を与える」のである(前掲論文)。
つまり、批判的思考のみへの着目は、雨漏りの修理をせずに雨漏り用のバケツを使いこなすよう推奨しているように聞こえるのだ。この場合、雨漏りとは尊厳の問題であり、バケツがメディアリテラシーである。
加えて、陰謀論を取り締まるという対策もあまり現実的ではない。意外に思う人も多いかもしれないが、前出のジョゼフ・E・ユージンスキは、陰謀論の禁止を求める声には反対している。陰謀論には必ずしも誤りではないものも含まれているからだ。
政府こそが、陰謀論と実際の陰謀の両方を提供する主体
ユージンスキは政府やテック企業が陰謀論を規制したり、埋もれさせたりしかねない現状について2つの皮肉があるという。「それは(一)陰謀論はおそらくは悠久の昔から人間の経験の一部であること、そして(二)政府高官や従来の報道機関は、自分たちに都合のよいときには陰謀論を広めるということだ」。そこには、「政府こそが、陰謀論と実際の陰謀の両方を提供する最大の主体である」という認識がある(以上、前掲書)。
わたしたちは、日常的な思考として、あるいはエンターテインメントとして数多の陰謀論に親しんでいる。それらは時に自らの重要性を強化したり、物語の刺激性に没入したりして、現実逃避を促進させるだけでなく、反社会的な行為に駆り立てることすらある。だが、その効用は個人が抱え込んでいる事情によって大きく異なる。
妙案はないが、どこかに利点がありうるという合理的な見地から、その真因を深掘りしていくことは非常に重要だ。とはいえ、社会関係資本が急速に崩壊し、人々が流動的で場当たり的な境遇を強いられ、承認のカオスに翻弄される寄る辺ない世界において、そのようなアプローチもますます困難になってきていることもわたしたちは知っておかなければならない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

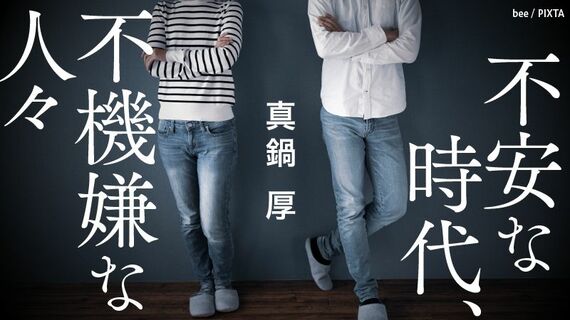































無料会員登録はこちら
ログインはこちら