「いらっしゃいませ」
ドアを開けて入ってきたのは四十を少しすぎた感じの女だった。
「あ、高竹さん」
高竹と呼ばれた女は、看護服に紺色のカーディガン、地味なショルダーバッグを持って入ってきた。少し息があがっているところをみると走ってきたのだろう、胸に手をあててあがった息を整えながら、
「電話、ありがと」
と、少し早口で言った。数はニコリとうなずき、キッチンに消えた。
高竹は一番入口に近いテーブル席に座る房木という男の側まで、二、三歩歩み寄った。 房木は高竹の気配にまったく気づく様子もない。
「房木さん」
高竹は房木に優しく声をかけた。まるで子供に話しかけるように。
房木は一瞬自分が呼ばれた事に気づかなかったのか、しばらくなんの反応も示さなかったが、目の端に入った人影に気づき、ぼんやり顔をあげた。
「高竹さん」
高竹の姿を確認すると房木は不思議そうな顔でつぶやいた。高竹は、
「はい、高竹です」
と、はっきりした口調で返事をした。
「どうしたんですか?」
「休み時間なんでコーヒーでも飲もうかと思って……」
「そうですか」
そう答えると房木は再び雑誌に目を落とした。
高竹はそんな房木を見つめながら、ゆっくりと向かいの席に腰を下ろしたが、房木は特になんの反応も示さず雑誌のページをめくった。
「待ってるんです」「あの席が空くのを……」
「最近、よくここに来てるみたいですね」
高竹がまるで初めて来た客のようにまじまじと店内を見回しながら、そう聞くと、房木は「ええ」とだけ答えた。
「お気に入りの場所なんですね?」
「別にそういうわけじゃ……」
否定しながらも、お気に入りの場所である事は間違いではないらしい。房木は、ほんの少し笑顔を見せて、
「待ってるんです」
と、高竹にささやいた。高竹が「なにを?」と聞き返すと、房木はワンピースの女が座るテーブル席に顔を向けて、
「あの席が空くのを……」
と、答えた。房木の表情は何やら少年のように輝いている。
聞き耳を立てていたわけではなかったが、狭い店内である。当然、房木の言った事は二美子の耳にも届いた。
(2023年1月1日配信の次回に続く)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

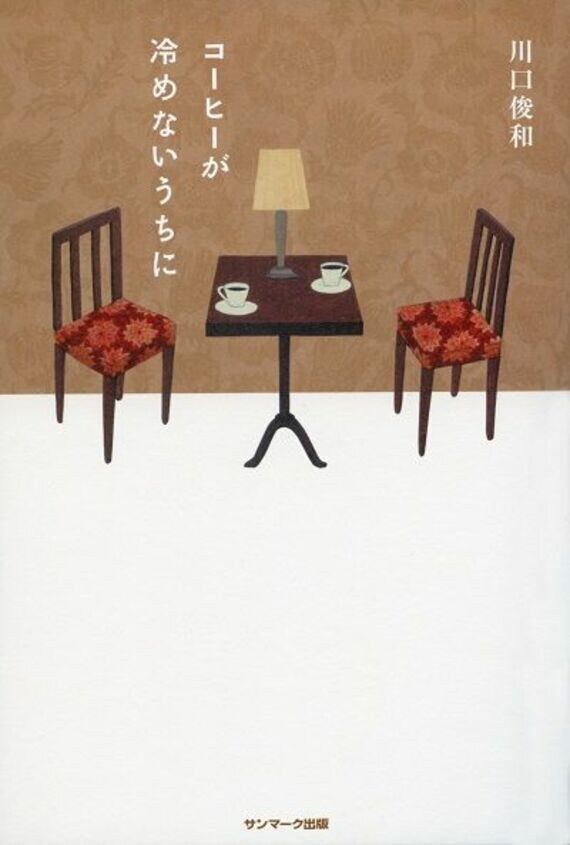





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら