病院では意外と大人しくしていたようだが、大の病院嫌いの父には苦痛だったはずだと智子さんは話す。
「以前に検査入院した際も、初日に着替えを取りに帰ると言って、病院には二度と戻りませんでした。若い頃から自称『ツボ押し健康法』を実践していて元気でしたし、病院で処方された薬も捨てる人なんです」

父の入院先から紹介された奈良の実家近くの老人施設に、5歳上で千葉在住の姉と母親との3人で面接に行った際、コロナ禍で入居後の面会は難しいと言われた。弱った父親を施設に1人きりにはできない、と改めて実家で看取る方向で話し合った。
「頼りがいのある訪問看護師や介護士さんも見つかり、以前からその存在を知っていた看取り士さんの支援も受けて、実家で看取ると決めました。帰宅後の父から実際に『ありがとう』と言われて初めて、ああっ、父も喜んでくれているって確信できたんです」(智子さん)
彼女は、一般社団法人「日本看取り士会」の柴田久美子会長の講演を、過去に2度聴いていた。柴田が提唱する「抱きしめて看取る」ことにも共感していたという。
「家族のために」父親を苦しませたくない
病院での延命治療を受けず、実家に連れ帰ることは、父親の生死に責任を持つことでもある。在宅医療の力を借りるとしても簡単な決断ではない。
「胃ろうや点滴は、父親の心身に苦痛を強いる面があることも知りました。自分の口で食べられなくなることや、誤えん性肺炎になるのは、寿命の終わりが近づいているという見方があることも、です」(智子さん)
個人差はあるが、最期が近づいた人の体は水分を吸収する力さえ失われる。点滴を注入しても顔や体が異常にむくんだり、痰(たん)が喉に何度もからんだりして息苦しくなる。痰の吸引が必要になり、その管の出し入れ時に喉などを傷つける可能性も高くなる。
智子さんは帰省した姉から、糖尿病で他界した父方の祖父の最期についても聞かされた。入院中の祖父は、体に装着されたチューブ類を自ら引き抜いて退院し、自宅で息を引き取った。父親は祖父を称賛していたという。
「家族ですから、『1日でも長く生きてほしい』という気持ちは当然あります。ですが認知症が進み、父の意思を確認できない中で、最期はできるだけ苦しまず、穏やかに過ごせる方法を選びたいとも思っていました。大の病院嫌いの父だから、その思いは強かったです」(智子さん)



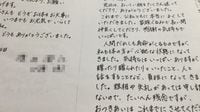



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら