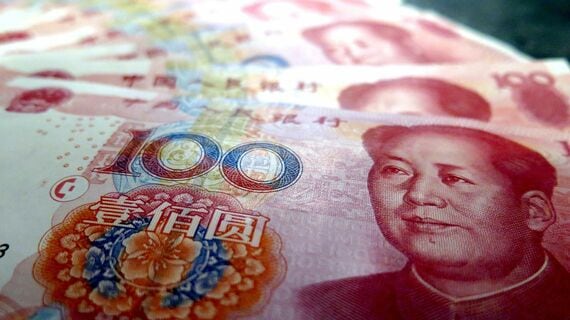
中国各地で新型コロナウイルスの流行が繰り返されるなか、市民の貯蓄がはっきりした増加傾向を見せている。中国人民銀行(中央銀行)が発表した最新データによれば、市民の貯蓄は2022年1月から5月にかけて累計7兆8600億元(約157兆2600億円)増加し、前年同期の増加額を50.6%上回った。
2022年5月末時点の人民元建て預金残高は246兆2200億元(約4926兆2960億円)と、1年前より10.5%増加。5月単月で見ると、人民元建て預金残高は(4月末時点より)3兆400億元(約60兆8234億円)増加し、前年同月の増加額より4750億元(約9兆5037億円)増えた。
貯蓄が増加する一方で、市民の消費意欲は低下している。新型コロナの防疫対策が各地で強化された4月は特に顕著で、同月の社会消費財小売総額は前年同月比11.1%減少した。さらに、5月に入って新型コロナの流行に歯止めがかかってからも、消費回復は勢いを欠いたままだ。
保有資産の増加にブレーキ
中国平安証券のチーフ・エコノミストを務める鐘正生氏は、消費の回復力不足の原因として次の3つの要素を挙げる。第1に、新型コロナそのものの影響による消費行動の抑制。第2に、家計が抱える債務の返済負担が重くなったことによる消費余力の低下。第3に、将来のリスクに備えた予防的貯蓄の増加による消費意欲の減退だ。

それだけではない。コロナ禍の打撃に加えて、(不動産市況の低迷長期化により)市民の保有資産の増加にブレーキがかかっている影響を指摘する声もある。
中泰証券のマクロ経済担当チーフ・アナリストを務める陳興氏の試算によれば、不動産を筆頭とする市民の保有資産の増加ペースは、コロナ禍のなかで明確に減速している。市民のさまざまな保有資産の総合的価値は、2011年から2019年にかけては年平均13%前後で増えてきたが、目下の増加率は1桁台に下がっているという。
(財新記者:王晶)
※原文の配信は6月11日
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



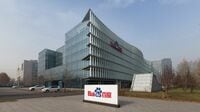



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら