「神道」が生きのびるために選んだ「変化」とは何か 宗教性の理解につながる「暗さ」や「悲の力」
喜界島において「神道はどのように生きのびてきたのか」という問いを立てることは、「民俗信仰はどのように殺されたのか」「仏教はどのように殺されたのか」という問いを考えることである。それと同時に、「(民俗信仰や仏教が)殺されたと見せかけて、どのように生きのびてきたのか」「神道は生きのびるうえで、どのような変化を遂げてきたのか」といった問いが、次々と派生してくる。これは喜界島に限ったことではない。
とりわけ最後の「神道は生きのびるうえで、どのような変化を遂げてきたのか」という問いに、本書は神道史を再構成することで委細に答えている。とは言え、高度にバランスの取れた選択的な叙述であるものの、読者の興味関心によっては「なぜこの神社について書かれていないのか?」「なぜこの人物について取り上げないのか?」という、「ないものねだり」が生じることだろう。
それにならえば、私としては朝鮮半島由来の神社信仰のルーツとして、宗像のほかにもう1つ、対馬についても島薗さんの見解を聞いてみたいところである。延喜式内社が29社と集中して存在し、朝鮮由来の天道信仰の聖地と神話を有し、石積みのユニークな石塔が島内に点在する対馬に、宮本常一や谷川健一、岡谷公二らは着眼したが、折口信夫は壱岐まで行って未踏に終わった。修士論文以来、折口に再びアプローチし始めた島薗さんの目には、対馬がどのように映るだろうか。
「暗さ」や「悲の力」が根源
最後に、本書のもととなった「島薗進ゼミ」の終了後、毎回おこなわれた「ラーメンを食べる会」で明かされたエピソードを紹介したい。
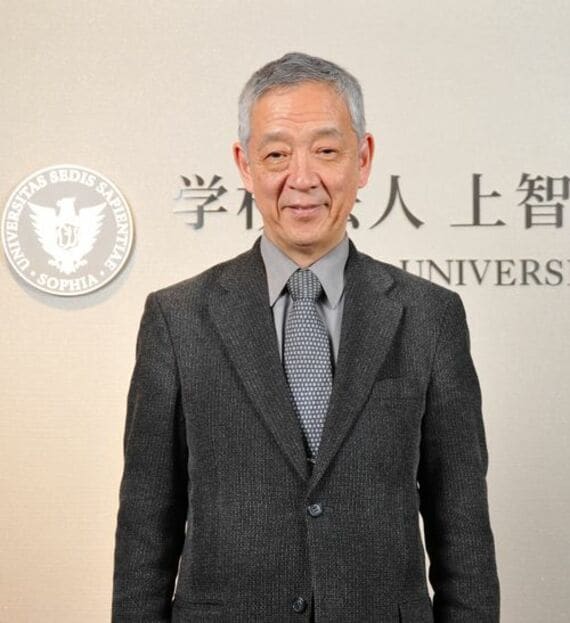
島薗さんは、カリスマ性や天性の明るさをもった研究者に対して引け目を感じてきたという。しかし、あるときから感じなくなった。それは作家の五木寛之さんを迎えて東京自由大学が主催したシンポジウムの際、五木さんが「暗さ」や「悲の力」が、宗教性の理解につながると述べたためである。
「暗さ」や「悲の力」こそ、50年間にわたる島薗宗教学の根源であり、コロナ禍と戦争の時代を生きる私たちにとって、これらの持つ創造的な側面に、ますます目を向けてゆくことが重要である。入門書の体裁を取ってはいるものの、本書はそんな島薗宗教学の精髄を十二分に味わうことができる。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら