日本史の「もしも」を考えることで見えてくる本質 ありえなかった過去の想像が未来につながる
例えば「大塩平八郎の乱」(1837)を例にします。江戸時代後期に、陽明学を学んだ大坂町奉行所の与力、大塩平八郎(1793─1837)が貧しい人々のために一揆を起こした。この事件などは、もし江戸幕府システムがしっかり機能している時期であれば「常軌を逸したやつが出た」くらいで話は終わっていたことでしょう。
ところが、実際にこの乱が起きたのは江戸時代後期。当時は商人が利益を上げ、貧富の差が非常に拡大し、システムにもだいぶボロが出てきていた時期です。大塩平八郎は、貧しい者を救うために豊かな者から米を奪った。いくら貧しい者に配布するためといっても、暴力的に実行してはいけないのですが、そもそも治安を維持する側の人間が逆に乱を起こしてしまったものだから、当時、大きな意味があったわけです。
「桜田門外の変」(1860)では、大老が暗殺されてしまった。江戸幕府システムがしっかりしている時期であれば、大老が暗殺されたとしても、事件のインパクトは「武士の恥だね」くらいで終わってしまい、体制を揺るがすようなことはなかったかもしれない。
「もしも」が物語を取り戻す
もっとも、システムがしっかりしていれば、大老を暗殺しようとする者は出てこないかもしれませんが、井伊大老の暗殺は、あの時期において、とてつもなく衝撃的な出来事でした。まさにあの事件によって「その時、歴史は動いた」わけです。
ただ「桜田門外の変」の場合、短いスパンで見るとその衝撃は大きかったですが、中長期的な視野で見ると、幕府はおそらくあの時点ですでに寿命は尽きていたのかもしれない。そこであらためてもう一度「桜田門外の変」を見直す。そうすると江戸幕府システムとはなんだったのか? 幕末の時代の社会の様相とは? そして「桜田門外の変」の本質はどこにあったのか? 「もしも」を考えることで、非常に多面的な視野が生まれてくることになります。
唯物史観は今まで「歴史にもしもはない」と言い切ってきました。あるものだけを見る。なかったものは見ない。それが科学的な見方であると。
その唯物史観に引っ張られて、われわれ歴史研究者も「歴史にイフを考えるのは邪道である」と考え、そう主張もしてきたのですが、もしイフを考えていいとなると、歴史は物語性を取り戻し、もっと面白い分野になることができる。とくに子どもたちにとっても興味深いものになるし、積極的に社会に発信していくことができるものになる。そう考えています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

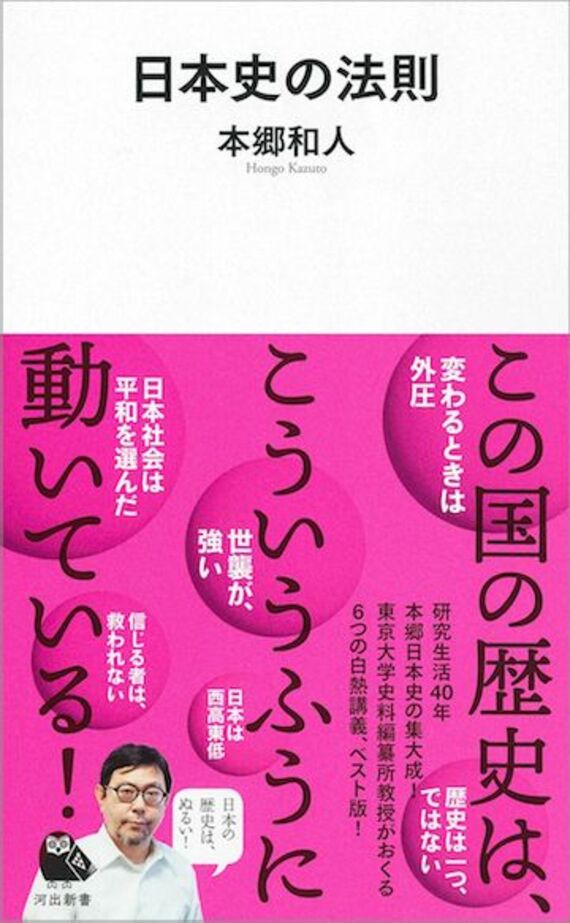
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら