市場ニーズがないとそもそもの採用枠が少ない(選考倍率が上がる)だけでなく、不景気では雇用が不安定になる。自分がやりたいことであっても、就職できない、就職してもリストラになる可能性が高い仕事であれば、選ぶべきではないというのが私の意見だ。
これはコロナ禍以前にもあったことだが、コロナ禍によって「とりあえず様子を見よう」という人がさらに増えたと感じている。
「コロナ禍の影響が判断できない」「何から手をつけていいかわからない」と言って様子を見ている人たちは、即行動に移している人たちに大きな差をつけられてしまう。
就活は以前にも増して早期化しており、採用解禁の3年生の3月よりもかなり前から選考インターンに参加し、内々定をもらう学生だけでなく、1年次や2年次から企業で長期インターンシップ(企業アルバイト)をしている学生すら出現している。
「様子を見る」という表現は、どちらかと言うとポジティブな表現として認識されているが、こと就活や仕事においては、「様子を見ている余裕」などない。何の狙いもなく様子を見るくらいなら、「やってみて情報収集する」ほうがはるかに効果的だ。コロナ禍のように周りの動きが見えない状況下においては、自分で行動し、情報を収集していく姿勢がより一層重要になる。
コロナ禍でも大事なことは変わらない
このように、コロナ禍での就活がうまくいかない人には共通の特徴がある。しかし、実はこれらの特徴は「通常時の就活」においても避けたほうがいいものばかりだ。
結局、次のように行動している人が就活で結果を出すことができる。
・選択肢や情報収集の機会を少しでも増やすため、「選考を受けるハードル」を必要以上に上げない
・相談できる人を、受け身ではなく、自ら探している
・「自分ニーズ」よりも「市場ニーズ」に重きを置いて活動している
・「ただ何となく」様子を見ない(状況が読めなくても行動しながら活路を見出す)
もし、現在の就活がうまくいっておらず、悩みを抱えている人は、YouTubeのUZUZ就活チャンネルや、Twitterで相談を受け付けているので、相談してみてほしい。
就活は孤独な戦いだ。だからこそ、相談できる相手を自分で探し、悩みを一人で抱え込まないで済む環境づくりが重要だ。就活がうまくいっていない人が、少しでも今の状況を好転させ、納得いく就活をしてもらえればと思う。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

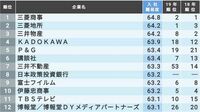
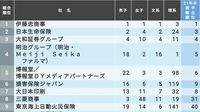






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら