新型コロナが引き起こす「MMTブーム」の第2波 パンデミック収束後の「新たな経済危機」とは
なぜ、そう言えるのか。
パンデミックの最中には、大規模な財政支出が行われる。しかし、その結果として、パンデミックが終わった後、膨大な政府債務が残される。
そうなると、財政規律にとらわれている国は、巨額の政府債務に恐れをなし、極端な歳出削減や増税によって、財政健全化を図ろうとするであろう。その結果、経済は、再び、恐慌へと陥ってしまうのである。
実は、これには先例がある。
世界恐慌時、アメリカのルーズヴェルト政権は、1933年から、ニュー・ディール政策の下、公共投資を拡大し、1935年までに失業率を減少させた。ところが、ルーズヴェルト政権は、景気回復の道半ばにもかかわらず、政府債務の累積に恐れをなし、1936年から1938年にかけて、財政支出を削減してしまった。その結果、1937年から1938年にかけて、史上最も急速な景気後退を引き起こし、失業率は再び跳ね上がってしまった。
つまり、1930年代、アメリカの恐慌は、2度、あったのである。アメリカが最終的に恐慌を脱出しえたのは、周知のとおり、第2次世界大戦に参戦したことによる軍事需要によってであった。
コロナ危機収束後、恐慌を引き起こしてしまう可能性も
この失敗が、コロナ危機においても、繰り返される可能性があるのだ。IMF(国際通貨基金)が、コロナ危機収束後の財政出動の必要性を説いたのも、おそらく、この世界恐慌の教訓を踏まえてのことと思われる。
だが、わが国では、健全財政論者からは、すでにコロナ危機収束後の増税を求める声があがっており、また政府も、依然、プライマリー・バランス黒字化目標という財政規律を撤回していない。なにせ、昨年、過去2度の消費増税の失敗にも懲りず、国内外の景気が後退している中で、消費増税を断行した国である。コロナ危機収束後、愚かな緊縮財政によって恐慌を引き起こしてしまう可能性は、決して低くはない。
しかし、もし本書が広く読まれ、緊縮財政の過ちが周知されれば、その危機を回避することはできる。そして、本書の処方箋が実行されれば、「失われた30年」からも決別できるだろう。
『MMTが日本を救う』が、日本を救うのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

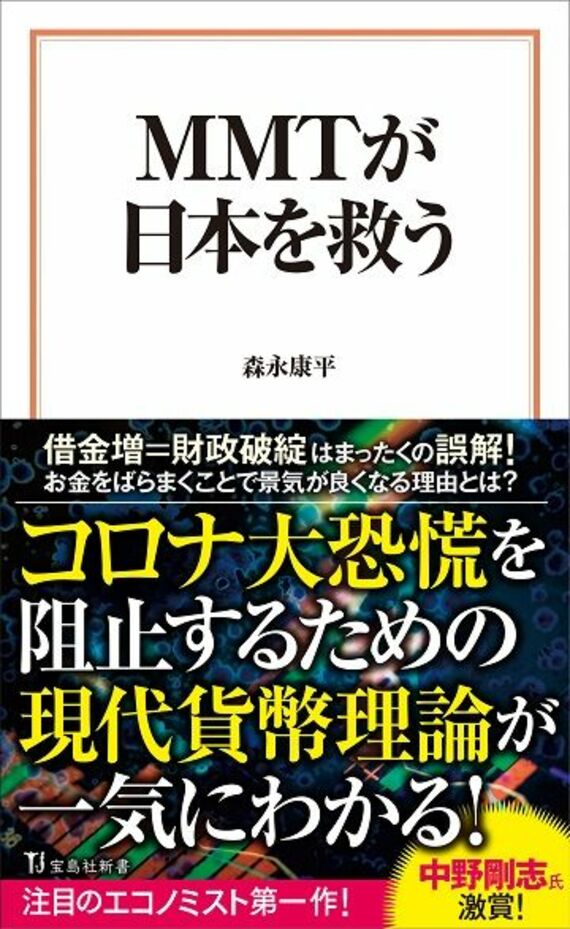
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら