コロナ騒動で激売れする小説「ペスト」の中身 今の騒ぎを彷彿とさせる冒頭部分を一部公開
タルーは髪の毛をうしろにかきあげ、今はもう動かなくなった鼠を再びながめ、それからリウーにほほ笑みかけた――
「しかし、要するにですな、こいつは何よりも門番の問題というわけです」
ちょうどその門番を医師はアパートの前で見かけたが、入口のそばの壁にもたれて、いつもは血色のいいあから顔に、ちょっとぐったりしたような表情を浮べていた。
「ああ、知ってまさ」と、ミッシェル老人は、新たな発見を知らせたリウーにいった。「なにしろ2匹だの3匹だのって見つかるんだからね、今じゃ。だが、こいつはほかのアパートでもおんなじなんでさ」
地下室から屋根裏まで鼠が散乱
彼の様子はいかにも打ちのめされたように、気づかわしげであった。機械的な動作でしきりに首をこすっていた。リウーは、体具合はどうかと尋ねた。門番は、体具合が悪いとは、もちろんいえなかった。ただ、どうも調子が十分でない。彼の意見では、つまり精神的なものが作用しているのだ。あの鼠どものために衝撃(ショック)を受けたわけで、やつらが姿を消してしまえば万事ずっと順調になるだろう。
しかし翌4月18日の朝、駅から母を迎えて来た医師は、ミッシェル氏がまた一層しなびた顔つきをしているのを見た。地下室から屋根裏まで、10匹もの鼠が階段に散乱していたのである。近所の家々の芥箱は鼠でいっぱいだった。医師の母親はその話を聞いても別に驚かなかった。
「いろんなことがあるものですよ」
黒いやさしい目をした、銀髪の、小柄な婦人であった。
「あたしはうれしいの、ベルナール、またお前の顔が見られて」と彼女はいった。「鼠だってなんだって、それをどうすることもできやしないさ」
彼もその言葉にうなずいた。そういえば、まったく、彼女の手にかかると、すべてがいつでも造作のないことに見えるのであった。
リウーは、それでも、そこの課長を知っている市の鼠害(そがい)対策課へ電話をかけた。課長は、大量に巣外へ出て来て死ぬ鼠どものうわさを聞いているだろうか? 課長のメルシエは、そのうわさを聞いていたし、河岸(かし)から遠くないところにある彼の役所でも、それが50匹ぐらい発見されていた。彼は、しかしながら、それが果してまともに考慮すべき事件かどうか迷っていた。リウーもその点はなんともいえなかったが、しかし鼠害対策課が乗り出すべきだと考えていた。
「うん、命令さえあればね」と、メルシエはいった。「君がもしそうするだけのことがあると思うんなら、ひとつ、命令を出してもらうようにやってみてもいいんだが」
「そりゃ、やればやるだけのことはあるさ、いつだって」と、リウーはいった。
家政婦が今しがた伝えたところによると、彼女の夫の働いている大工場では、死んだ鼠が何百匹となく拾い集められたという。いずれにしても、ほぼこの時期において、わが市民は不安になり始めたのであった。
(冒頭後編に続く)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

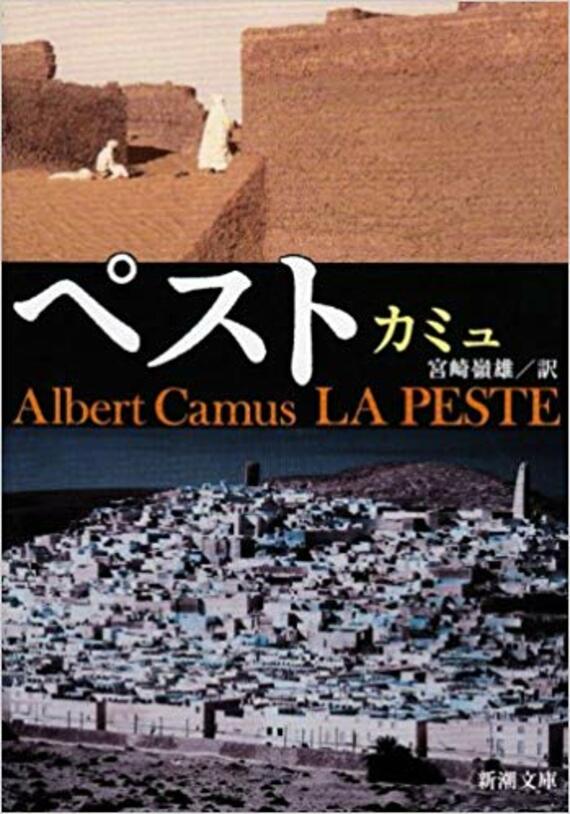

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら