
2020年が明けた。北陸新幹線は3月に金沢開業5周年を迎え、一方で敦賀開業が3年後、2023年春に迫る。新たな終点・敦賀は「鉄道と港のまち」をうたう、古代にさかのぼる「境界」の地だ。年間980万人と見込まれる乗換客にどう対応し、まちの基礎や文化をつくり直していくか。在来線と新幹線の「境界のまち」となる敦賀の模索が始まっている。
駅舎に災害対応機能
北陸線と小浜線の乗換駅・敦賀は1882(明治15)年に開業した。駅舎は小ぶりながら、昭和の香りを残す地下道と、2012年にリニューアルされたエレベーターやエスカレーターを併せ持つ。大阪から特急「サンダーバード」が湖西線・北陸線経由で、名古屋から「しらさぎ」が東海道線・北陸線経由で乗り入れる。ホームでは今なお、電球が付いた案内表示板が、到着する特急の種類を知らせてくれる。
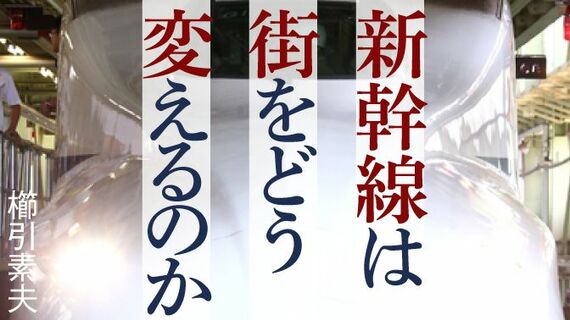
駅前広場は、黒い柱やキャノピー(通路屋根)の鋭角的なデザインが印象的だ。こちらは2014年、駅舎と一体化している交流施設オルパークとともに整備された。交流施設は待合室機能と観光案内所、物販、多目的室などを備え、「駅を拠点にしたまちづくり」を意識した公民館の趣がある。季節を変えて訪れる都度、高校生たちが勉強する姿が目に留まった。こんな若者たちにとって居心地がよい駅は、地域の大切な財産だ。

タクシー乗り場の横、植え込みに設置されたソーラーパネルが目に留まった。あまり見かけない取り合わせだ。市によると、災害対応を視野に入れた設備だという。駅前広場の電力確保に加え、東日本大震災などを教訓として、災害時に駅利用者らが携帯電話を充電できる機能を備えている。鉄道駅の進化に驚かされる。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら