大阪生まれの親子らしい、からっとしたやり取り。それは父と中屋敷それぞれの、「死の受け入れ」宣言だったのかもしれない。反対に、本人は死を受け入れているのに、家族が受け入れられない場合もある。
「自分が妻の命に執着すると、妻を苦しめる」
日本看取り士会から、中屋敷に末期がんの女性の看取り依頼があった。元経営者の夫が、「緩和ケア病棟への泊まり込みの介護で、自分の代わりに週3日入ってほしい」という。夫が疲労困ぱいで倒れたためだった。
彼の妻は延命治療を拒否。同じ病院の緩和ケア病棟に、彼女自身が希望して移っていた。自力ではもう食事もとれなかった。
「奥様はもう話せない状態でしたけれど、表情はとても穏やかでした。ご自身はすでに死を受け入れていらっしゃるようでしたが、依頼者であるご主人は、まだ気持ちの整理がつききれていないご様子でした」(中屋敷)
介護福祉士でもある中屋敷が、24時間介護に入っていると、夫の兄弟たちが毎日お見舞いにやって来た。女性は夫の会社の経理を長く務め、兄弟や部下の面倒見もとてもよかった。また、どこに行くのも夫婦一緒という、仲の良さでも知られていた。
「ご主人ががんに効くとどこかで聞かれた明日葉を、自宅でとろとろに煮込んで持参されるんです。ポン酢をかけて、『僕のために食べて』と哀願されると、奥様も懸命にひと口ふた口を飲み込まれる。その姿が切なかったです」
妻は自身の死を夫が受け入れてくれるのを、我慢強く待っている。中屋敷にはそう見えた。翌日、夫が看取り士を依頼した理由を教えてくれた。
「看取り士のことは以前から知っていたが、気持ちの整理がなかなかつかなかった。しかし、私が妻の命にこれ以上執着すると、妻を苦しめることになる。自分が気持ちを切り替えなければと考えて、お願いしたんです」
だが、実際には看取り士を依頼した後も、夫は少しでも食べさせようとしていた。最愛の妻の死を受け入れることは一筋縄ではいかない。
「ご本人とご家族で、死を受け入れるタイミングにズレが生まれることは多いんです。そのズレを調整するのも看取り士の役割の1つです」(中屋敷)
翌週、妻は息を引き取った。最期は夫が抱きしめて看取ったという。事前に中屋敷に教わっていた作法通りだった。
「ご自宅でなくても、病院でも、老人施設でもいいんです。触れ合うことができれば、悲しくても、幸せに看取ることができます」
兄のときは遺体に触れられなかった中屋敷が、最後にそう念押しした。
(=文中敬称略=)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



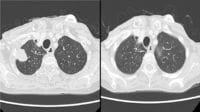






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら