原因がよくわからない「吃音」の不思議な現象 なぜ人は「どもる」のか?

"ここで不思議なことが起こります。スタジオには、同じく吃音当事者の落語家、桂文福さんがゲストとして来ていました。その文福さんが、吃音症状の出ている八木さんに向かって、「タン・タン・タン」と規則的に舌を打ち始めたのです。商売道具の扇子を横に振りながら、口拍子をとっていく文福さん。すると、まるで金縛りが解けたような変化が起きたのです。数秒前の吃音症状はどこへやら、なんと八木さんが別人のようにしゃべり始めたではありませんか。"
こんなエピソードがカバーの折り返しに書かれていて思わずそそられる。さらに謎めいた表紙のイラストや「しゃべれるほうが変。」というコピーも合わさって、不思議な雰囲気が醸し出されている。
本の体裁にもよく表れているように、吃音はどこか謎めいた現象である。今から100年以上前の日本でも、吃音をいかに直すかの試行錯誤がなされていた(その動きは現在よりも活発だった)そうだ。しかし今日に至るまで「治るのか治らないのか」について統一された意見はなく、原因が何なのかも完全には解明されていない。
この謎多き現象について本書『どもる体』が行うのは、原因探しでも、治療法の提案でもない。
障害があるから「こそ」生まれる斬新な認識
“本書は、あくまで「どもる」という身体的経験にフォーカスを当てます。それを乗り越えるべき症状としてではなく、体に起こる現象として観察したいのです。”
この視点は、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』『目の見えないアスリートの身体論』といった著者の前作、前々作から引き継がれているものだ。外側に現れる「症状」ばかりではなく、その人の内側で何が起こっているのかに注目することで、障害があるから「こそ」生まれる斬新な認識、体の動きが見えてくる。そこあるのは必ずしもネガティブな面ばかりではなく、非当事者が持ちえないような粒度で身の回りの世界に触れるという意味で、ポジティブな面も少なくない。
そうした話を、啓蒙っぽくならないようなニュアンスで興味深く伝えてくれるのが過去作から共通した特徴だ。「身体論からみた吃音論」と銘打たれた本書のアプローチは、このような流れの中にある。





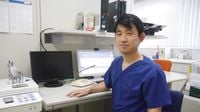





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら