障害児向け「エリート校」が生まれる根本理由 都が鳴り物入りで進める特別支援教育の正体
たとえば、知的障害のある子どもの場合、同じことを教えても理解度にはばらつきがあり、なかには目に見えた成長がほとんど見られない生徒もいる。身体障害では、知的能力にほとんど問題がなく車いすで移動できる子どももいれば、ストレッチャーに仰臥したままの重度の生徒もいる。
生徒本人たちの教育的ニーズがバラバラかつ不明確で、成果も見えにくいということになると、いきおい学校としては保護者や教師の利害を優先させることになる。保護者の場合は、わが子とはいえ24時間共に過ごす苦悩から解放されたいという欲求がある。そんな保護者にとって学校は無料のレスパイト(ひと休み)提供機関となるだろう。
他方、教員は生徒や保護者からの明確なニーズの提示がなければ自らの教育理念に基づいて行動するしかなくなる。そのひとつが「障害のある子たちにも普通校の生徒と同じ経験をさせてあげたい」というものだ。特別支援学校では、運動会、文化祭、修学旅行などがその教育的意義について深く検討されることもなく実施される。そこには現場の努力と相応のリソースが要求されるため、まさに教師たちの熱意によって成り立っている行事といえる。
軽度障害児のための"エリート校"と受験対策塾
このような学校生活を終え社会に出る段階になると、障害児や保護者には試練が待ち構えている。それは次の行き先である。文部科学省の調査によれば、2012年3月における特別支援学校高等部(本科)卒業生の進路は、知的障害児で福祉施設が66.7%、企業就労が28.4%となっており、肢体不自由児では施設が80.4%、就労が10.5%となっている。つまり、多くは福祉施設に入所しているのである。
ほとんどの卒業生が障害者施設に入り、そこで単価の低い単純作業をするのであれば、学校は何のために存在しているのかという批判が出てもおかしくない。施設職員の数倍の給与をもらっている教員に対し、目に見える成果を出すようプレッシャーがかかるようになったのである。
そこで学校は成果が見えやすい"就労支援"に力を入れるようになる。前回(日本の「障害者雇用政策」は問題が多すぎる)も触れたように、日本の民間企業は従業員の一定比率にあたる障害者を雇うよう義務づけられている。この"法定雇用率"は2013年に1.8%から2%、2018年には2.2%へ引き上げられた。そして、2020年には2.3%まで上がることが予定されている。この度重なる法定雇用率引き上げに対応するため、企業は働ける障害者を確保しようと必死になってきた。
この"追い風"にいち早く乗ったのが東京都教育庁である。なぜ東京なのかは容易に察しがつくだろう。東京には企業が集積しており、いきおい障害者に従事させる間接業務が多く存在しているからだ。
具体的には、企業就労率100%を目標に、職業開発科と就業技術科がこれまで都内にある7つの特別支援学校に設置されてきた。そこでのカリキュラムは、1年次に事務、清掃、介護などの作業を一通り経験し、2年次に就労分野を絞り込み、3年次に就労先を定めて専門的な知識と技術の向上を図るという内容だ。
入学の際には、カリキュラムに適した能力を備えているかどうか確かめる適性検査もある。まさに企業就労を目指す障害児のための"エリート校"といえる。これがどのような事態を招くかは一目瞭然だろう。すなわち、入学を目指す障害児のための塾の誕生である。将来の就職がかかっているのだから、本人はもとより親も受験に熱を上げるのは無理もない。

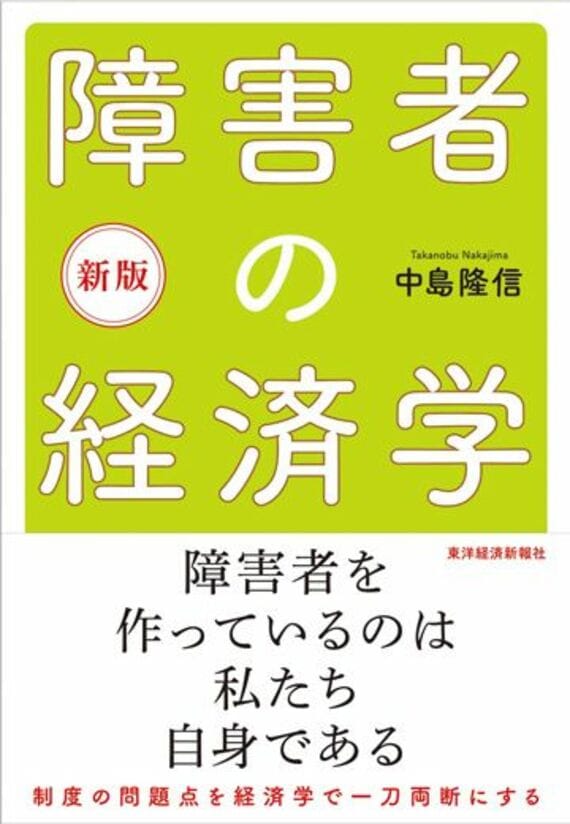






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら