21世紀の太宰治、その言葉はSNSで「拡散」する 熱狂的な信望者とアンチを生み出した作家
これまで太宰ファンには、政治運動の挫折、精神病、心中といった、ショッキングで破滅的な、ゆえに魅力的な「太宰神話」を抱く人が多かった。僕もそのクチである。逆に、この「太宰神話」のせいで食わず嫌いになってしまった人もいたかもしれない。しかし、小説家太宰治の本領とはむしろ、どんなにシリアスな場面でもどんなに苦しい場面でも、どこかそんな自分を俯瞰して、自分で自分のことを笑ってしまうような感覚にあるのではないか。あるいは逆に、一生懸命に、切実にふざけているような感覚にあるのではないか。
マジでいるときほど、そのマジさを滑稽に思ってしまうような感覚。反対
に、きわめてマジな態度でふざけているような感覚。本当か嘘か? 切実か軽薄か? そんな簡単に切り分けられないようなものこそ、太宰作品が描いてきたものだ。だとすれば、破滅的な無頼派としての太宰治像は、そのゆたかな作家像のほんの一側面に過ぎない。むしろ、苦しく切実な場面でふと見せる愛らしい表情を見逃してはならない。昨今の太宰リヴァイヴァルにおいては、そんな太宰の愛らしい表情が親しまれているように思える。
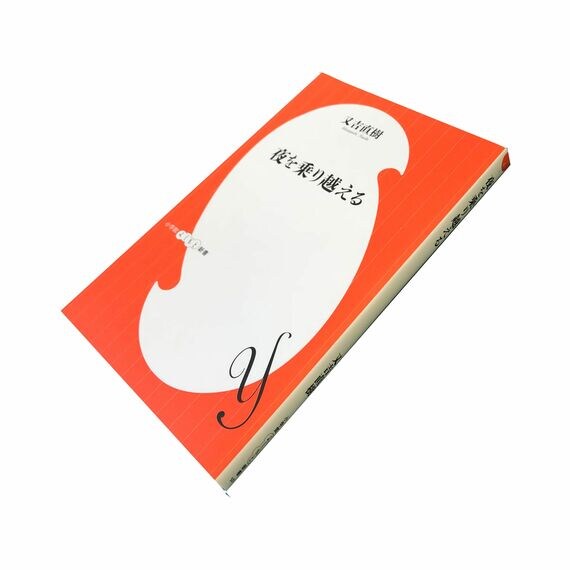
このような太宰の愛らしい魅力を引き出した人として、芸人「ピース」の又吉直樹さんを挙げないわけにはいかない。根っからの読書好きで、いまや芥川賞作家でもある又吉さんは、文学作品の熱心な紹介者として、多くの人たちを文学の世界にいざなった。なかでも、又吉さんは太宰に関して思い入れが強く、太宰生誕100年の桜桃忌(6月19日)には、太宰について語り合うイベント「太宰治ナイト」を主催した。木村さんも参加者のひとりとして名を連ねる「太宰治ナイト」は、毎回テーマを決めて太宰治について話したり、太宰作品をモティーフにしたコントを披露するなど、太宰のユーモラスな部分が強調されたライブである。好評につき、2009年以後現在にいたるまで、継続的に開催されている。
そんな又吉さんが太宰と出会ったときのことが、著書『夜を乗り越える』
(小学館よしもと新書)のなかに書かれている。又吉さんは、「『人間失格』を読んだ時、その内容に衝撃を受けたのと同時に、こんなダウンタウンさんみたいな感覚の人がお笑いの世界以外にもいるのかとも思いました」と書いている。興味深いのは、又吉さんが、ダウタウンと並列して太宰治を捉えていることだ。又吉さんが太宰とダウンタウンに共通して感じたものは、「みんなの共感や、新しい感覚の発見」だという。なるほど、たしかにダウンタウンの松本人志さんは、なにげない日常のなかに存在する微細な違和感をかたちにすることで笑いをもたらす。言われてみれば、太宰作品の語り手が作中人物に向ける視線は、愛と意地の悪さに満ちた松本人志さんの視線に通ずるところがある。又吉さんの功績はなにより、太宰作品の魅力をお笑いの感覚の延長で捉えた点にある。又吉さんの影響で太宰に触れた新しい読者にとって、太宰作品は楽しいものとして開かれているのだ。
ひたすら可笑しく哀しい、究極の人間らしさ
このような太宰リヴァイヴァルのなかで、あらためて『走れメロス』に注目してみる。『走れメロス』と言えば、中学校教科書にも採録されている有名作品で、メロスとセリヌンティウスの友情物語として知られている。しかし、よく読んでみると、そんな単純な話でないことがわかる。冒頭のメロスと王のやりとりもなんだかヘンだし、そもそもメロスはほとんど走っていない疑いすらある。おまけに、最終的にメロスはなぜか裸になって物語は終わる。
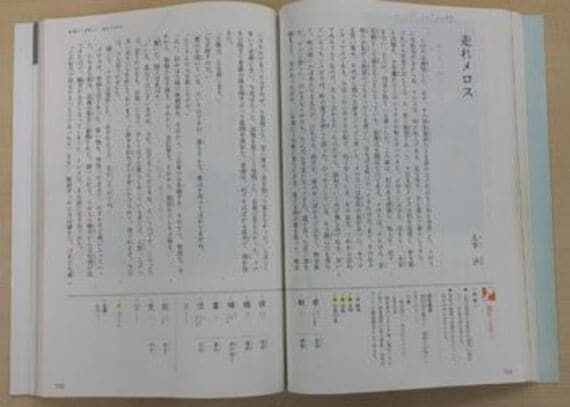
ようするに、『走れメロス』には、作者である太宰の意地悪な視線がたっぷりと含まれているのだ。どんなにシリアスな場面に見えようとも、メロスには滑稽さがつきまとっている。「太宰神話」から自由になったいま、『走れメロス』から読み取るべきは、そのような、作品に仕掛けられた太宰一流のサーヴィス精神である。
いや、それだけではない。そうやってメロスの滑稽な部分に目を向けると、今度は、そんなみっともないメロスが、それでも自分なりに、山を越え、川を越え、セリヌンティウスのもとに前進し続けていることに妙に胸打たれてしまうのだ。マジであればあるほど滑稽に見える。滑稽なほどの一生懸命さに胸を打たれる。その姿がまるごとチャーミングで愛おしい。この不思議な魅力をもった作品は、「太宰治ナイト」でも笑いとともに精読されていた。イベント登壇者の木村さんは、イベントを振り返りながら次のように言う。
「『走れメロス』もまさにそうなんですが、人間の生を突き詰めると、ひたすら可笑しくて悲しいんですよね。究極的に人間らしい振る舞いをしているときの人間は、すごく滑稽だし、同時にすごく悲しい。そういうものを太宰は描いている。つまり、太宰は人間を描いている」

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら