「間断のない移動」をめざした、戦前の労働行政
いったい、どうしてそんなことになったのだろうか。菅山真次『「就社」社会の誕生 ホワイトカラーからブルーカラーへ』は戦前にまで遡って、この「間断のない移動」を国民全員に要請するしくみが、形成される過程を明らかにしている。
菅山氏の調査した八幡製鉄所の事例によると、20世紀初頭の時点では、高等教育を終えて技術者として入社する場合には9割近くが「新卒採用」だったのに対し、技術職でも中等教育卒であるか、または高等教育卒でも事務職員の場合は、新卒採用の比率は2割程度となっている。
また、新卒で採用された者の出身校の多くは、帝国大学をはじめ理工系の学科をおく名門校に偏っていた。つまり大正時代の頃までは、今日の英米と同様に「専門性の高いエリート社員」だけが卒業と同時にリクルートされ、他は転職や中途採用のコースで雇われていたのだ。
ところが、1920年代の後半からこれが一変して、事務職員や中等教育卒も含めて、ホワイトカラーであれば「新卒採用が原則」と位置づけられるようになってゆく。
確かに当時は小津安二郎の映画『大学は出たけれど』(29年)が流行したように、長期不況と学歴インフレのため、「エリート大卒者」のプレステージが減少した時代ではあった。しかし菅山氏の見るところ、この変化の背景には「間断のない移動」を社会秩序のあり方として是とする、国家的な思惑もあったらしい。
すなわち小学校卒も含め、より若年での就職を斡旋する少年職業紹介に関して、25年に内務省社会局と文部省が連名で通達を出して以来、可能なかぎり学校と職場を直結させて、卒業から就職までの間に「すきま」を作らせないことを理想とする政策が打たれたというのである。
学校にも企業にも所属しない状態で若者をブラブラさせると、不良少年化して国体を損ねるという発想が、戦前の官僚には強く存在したようだ。
というよりもむしろ、学校を出てもすぐさま別の機関に入って、必ず自分が「所属する組織」を持ち続けなければならない、とする人生モデル自体が、今日にまで続く新しい「国体」になった、と捉えるべきかもしれない。

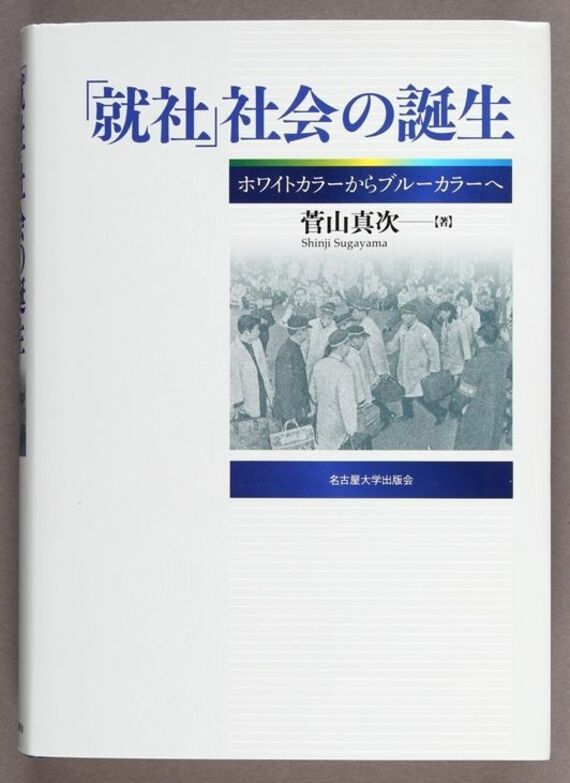
![ユニクロ 疲弊する職場 [拡大版]](https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/1/b/200w/img_1be86ff087a6df305199919478731a0417950.jpg)































無料会員登録はこちら
ログインはこちら