育成責任を現場に負わせる前に、教える側になったときにどのようなことが必要になるのかをマネジメントが明らかにするべきです。そのうえで、指導経験に応じて、教える側の姿勢を整えることが、組織の中でOJTの質を高めることにつながります。
日本的サービスの伝承
ご紹介した舞妓さんの事例は、現場のほんの一コマです。
京都花街では、こうした日常の現場の積み重ねを通して、マニュアル化が困難なきめ細やかな日本的サービスを、10代の女の子たちに指導しているのです(この点については、『プレジデント』2013年4月1日号で加護野忠男先生が詳しく解説されていますので、ぜひご参照ください)。
教わる側の姿勢を作ってから現場に出す。現場では常に行動のチェックと具体的な言葉かけを実施する。さらに教える側の姿勢も、より経験の長い先輩や経営者側がチェックする。
これらが密接に結び付くことで、教えてもらえるという安心感が未熟な若者の不安感を軽減し、職場で自分のポジションを認められる自信につながるだけでなく、後輩と先輩の良好な人間関係形成にも貢献します。
中小事業者や個人自営業者の集まりである京都花街では、技能形成と質の高いサービスを提供するという共通の目的のために、誰もがOJTを必須のものと認識し、積極的にかかわっています。
その結果、京都花街全体が有機的な組織のように機能し、新しく京都にやってきた現代っ子の若者を伝統文化の担い手、高付加価値のサービス提供者に育成していくことができるのです。
次回は、キャリア3年目、少し慣れてきた舞妓さんのOJTの事例を紹介します。新人時代を乗り切って、次の壁が見えてきた頃には、どのようなことがポイントになるのかを、解説したいと思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


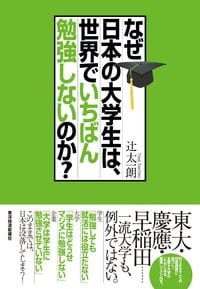





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら