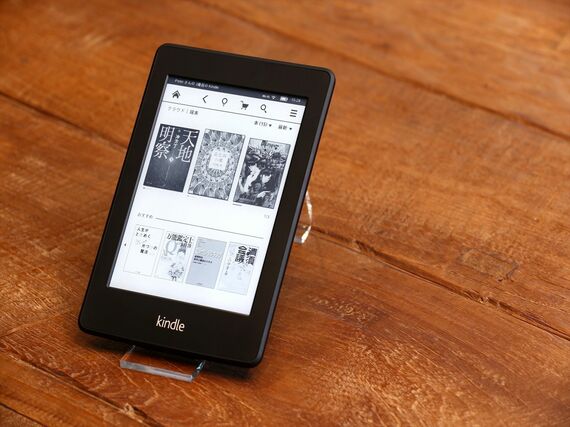
ある中堅出版社の社長と飲んだ。その席で、酔った社長から「山田さんは電子の人だから」と言われてショックを受けた。私が「冗談でしょう」と言っても、「うちの社員は皆そう思っていていますよ」と言い返されて、さらにショックを受けた。
この社長は40代の半ばで、私より一回り若いのに、根っからの「紙人間」である。つまり、「電子書籍なんか本ではない」と思っていて、私の新著『出版・新聞 絶望未来』も真っ先に読んでくれたのだが、それでも「山田さんはやはり電子の人」と言うのである。
もちろん、私は自分を「電子の人」などと思ったことは一度もない。
電子書籍制作をやってはいても、それはいずれ電子書籍時代になったら困るからであり、心のどこかでは「電子書籍時代なんて永遠に来てほしくない」と思っている。「でも、この本のタイトルでは、そう思われても仕方ありませんよ。電子化推進の本としか思えませんからね」と、社長は続けた。
確かにそのとおりかもしれない。私としては紙への愛着を持って書いたつもりだが、タイトルだけを見れば、そう取られても仕方ない。なにしろ『出版・新聞 絶望未来』である。しかも、私は「好むと好まざるとにかかわらず、紙の時代はやがて終わる」という前提で書いている。
これまで、電子書籍関連の本は何十冊も出版されている。そのほとんどが、すぐにでも電子書籍時代はやって来る、電子書籍時代になったら、出版社、作家、読者はこう変わる、などということが書かれていた。
つまり、「電子書籍化大歓迎」本、「電子書籍化推進」本である。しかし、私は電子書籍化を「歓迎」も「推進」もしていない。電子書籍化反対とまでは言わないが、むしろこのまま電子化が進むことに極めて懐疑的な立場を取っている。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら