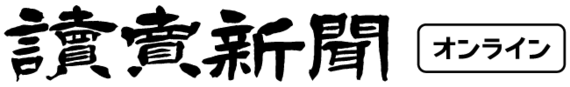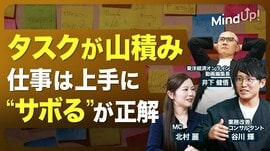佐賀市、学童保育の待機児童数を11年間国に過少報告か/一部で受け入れ対象を3年生以下に限定

佐賀市が、共働き家庭などの小学生を預かる「放課後児童クラブ」(学童保育)の利用について、条例で全学年を対象としながら、一部の校区で1~3年生に限定していたことが21日、わかった。高学年は利用申請を受け付けておらず、待機児童数などを調べる全国調査に対し、2015年から11年間にわたって、実態より少なく報告していた可能性がある。(小林夏奈美)
市では、国の方針を踏まえ、15年に学童保育の受け入れ対象を小学3年生以下から、全学年に拡大した。しかし、スタッフや施設の整備不足などから全学年を受け入れられず、市は各校区ごとに確実に受け入れることができる学年までを推計して募集し、利用を制限していた。現在、6年生まで受け入れられているのは、全35校区のうち19校区にとどまっている。
一方、調査は、こども家庭庁が、全国の各自治体を対象に、待機児童数の実態を把握するため、毎年実施している。
市は、利用申請をしたが、利用できなかった人数のみを待機児童数として県を通じて国に報告していた。このため、高学年の利用申請を受け付けていない校区については、そもそも利用申請がないため、待機児童として数えられていなかった可能性がある。
市の担当者は「申請には勤務証明書などの書類をそろえる必要がある。受け入れられない保護者の負担を軽減するためだった」などと説明している。
同市は他自治体の推計などを基に、待機児童を解消するためには3900人の受け入れができる施設が必要とし、27年4月までに全学年を完全に受け入れることを目標に定めている。
坂井英隆市長は21日の定例記者会見で「調査については国や担当部署に確認し、その上で対応を考えたい。問題の本質は高学年までの受け皿ができていないことにある」と話した。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら