また、日本人は「和」を重んじます。共同体の中で安全に暮らすために、協調性を大事にしてきました。「人様に迷惑をかけてはいけない」と親から言われ育ち、その価値観を貫いてきた人も多いでしょう。それは日本の素晴らしい文化です。
とはいえ、集団に配慮するからこその弊害もあります。
「自分だけ休暇を取るのは申し訳ない」、「休んだら迷惑をかける」という心理は、和を重んじるがゆえに生じるもの。和を乱す人物だと思われると集団の中で生きていけないという思考が現代人の中にもあるのです。これも、休むことへの罪悪感の要因になっています。
休むことができない「外的要因」
90年代初頭にバブル経済が崩壊し、日本の生産性は伸び悩むようになりました。そんな中でも多くの人は自己犠牲型の労働を続け、うつ病や過労死が増え、社会問題になりました。自殺者が年間3万人を超える状況も長く続きました。
その状況を受けて2019年に働き方改革関連法が施行されます。
残業規制や年休取得の推進などが次々と目の前に現れ、これまでのモーレツな働き方とは真逆の働き方に変えなさいと、ある日突然告げられたわけです。
心がついていかないのも当然です。とりあえず残業規制をしているものの、限られた時間の中で生産性を上げるために何をしたらいいか明確な答えがない中、どの企業も手探りでここまで進んできました。
だからこそ、課題が山積しています。私たちが休めないのは、罪悪感だけではありません。混乱する職場環境や旧態依然とした文化など、外的要因もいくつかあります。
なんといっても、業務の属人化が大きな課題です。
日本の多くの職場では、個人の能力に頼り、マニュアル作成や知識の共有を軽視してきた傾向が強く、結果として属人化が進みました。加えて、人手不足が加速し、誰かが休むと代わりに対応できる人がいないため、休みが取りにくいのです。
さらに、いまだに長時間働いている人のほうが評価される職場もあります。そのような職場では、休暇の制度は形骸化しています。
内的要因と外的要因。いずれも一筋縄ではいかない課題ですが、1つずつ乗り越え、戦略的休暇を習慣化させることを目指しましょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

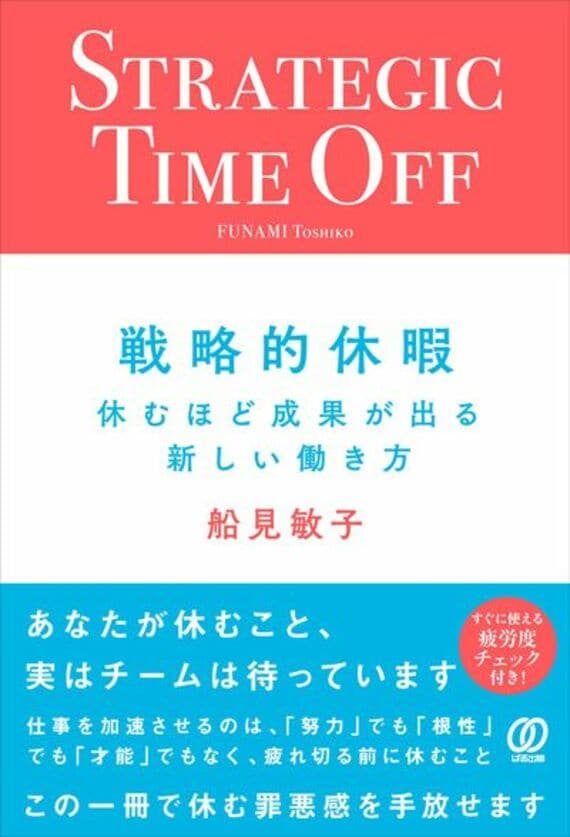
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら