「どうやって接すればいいんだ?」経験豊富な上司ほど悩んでいる 若手部下との"適切な距離" 今すぐできる4つの改善策
ある40代の部長は、こう語った。
「若手にメールを送ると、返信が『了解です』の一言だけ。失礼じゃないかと思ってしまう。でも本人は悪気がないんだろう。どう受け止めたらいいのかわからない」
世代の壁は、10歳を超えると急に高くなる。それは文化の違いであり、コミュニケーションの土台が異なるからだ。
「距離」が見えない時代の難しさ
人間関係には「パーソナルスペース」という心理的な距離がある。相手との物理的な距離だけでなく、どこまで踏み込まれて心地よいかという心の領域だ。
アメリカの文化人類学者エドワード・T・ホールは、人と人との間に存在する距離を「近接学」として体系化した。彼は対人距離を4つのゾーンに分けて説明している。簡単に解説しよう。
家族や恋人など、ごく限られた関係に許される距離。
友人や同僚との会話にふさわしい距離だ。
初対面やフォーマルな関係に適した距離である。
講演会やスピーチなど、多人数を相手にする際の距離。
人は無意識にこのゾーンを使い分けながら、相手との関係を調整している。私はよく講演することがあるが、最前列の人との距離があまりに近いと、とても居心地が悪くなる。やはり公的距離(360cm以上)はとってもらいたいと思う。
営業とお客様、上司と部下とのパーソナルスペース(物理的距離)も、適切に調整することが大事だ。これを「人間(じんかん)距離」と名付けている方がいた。「車間距離」にたとえた表現だ。
車を運転するとき、適切な車間距離を保って運転することが大事だ。それと一緒。人と人との「人間距離」も、常に意識して調整すべきだ。そうでないと「事故る」ことが増える。
28歳の先輩は、この距離感を自然と理解していた。23歳の後輩が心地よいと感じる距離を、感覚的につかんでいる。実際のところ、先輩(28)は後輩(23)を「マサ」と呼び、後輩もまた先輩を「タケ」と呼び捨てにしていた。
「タケって、こういう商談のとき、どうするの?」
「ああ、それは企業データベースを参考に3つの情報を事前に確認しておけばいいよ」
「了解!」
こんな感じなのだ。




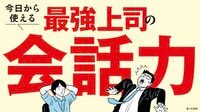


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら