そんな小細工が、なおさら幕府の怒りを買ったらしい。蔦重は「身上半減」、つまり、財産を半分持っていかれることになり、京伝にいたっては「手鎖50日」で、手錠をしたまま50日にもわたって、自宅で謹慎させられることになった。
その後、しばらく京伝の執筆意欲が失われたことは言うまでもない。
寛政4(1792)年には、蔦重は勝川春朗の『実語教幼稚講釈』を刊行。画には「山東京伝」がクレジットされているが、実は他人による代作だった。その人物こそ、のちに『南総里見八犬伝』で歴史に名を刻む、曲亭馬琴である。
過酷な幼少期を経て戯作の世界に飛び込む
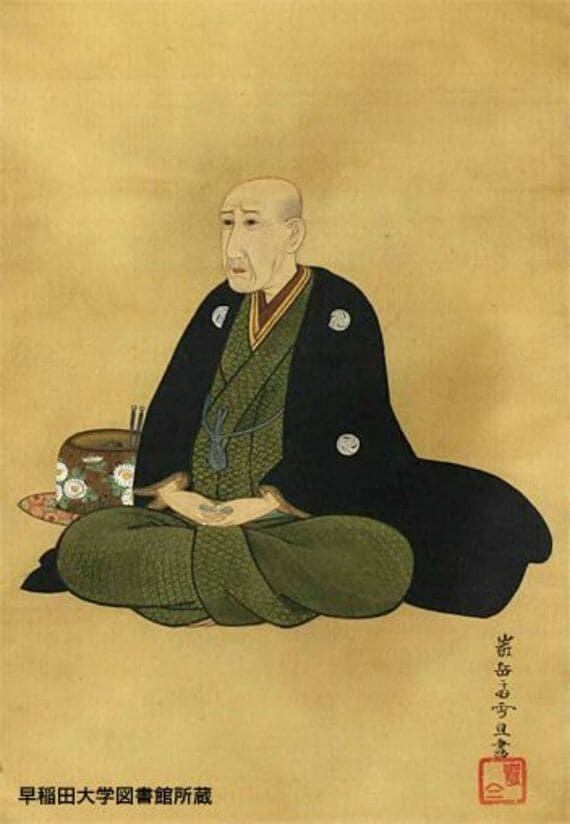
馬琴は幼名を「倉蔵」といい、明和4(1767)年に江戸の深川にて、滝沢興義(おきよし)の5男として生まれた。父・興義は旗本・松平信成の用人を務めており、馬琴やその兄たちに四書五経を学ばせて、俳句も教えた。
だが、馬琴が9歳のときに酒が原因で死去すると、兄たちも出ていくなどして、一家は離散。馬琴はわずか10歳にして、家督を継ぐことになる。
困窮するなか、主君の孫に小姓として仕えるが、幼君はひどい癇癪持ちだった。人間扱いされない日々に堪えかねて、14歳で出奔。主家を転々としたのち、24歳のときに馬琴は酒一樽を持って、京伝のもとを訪れている。弟子入りを志願するためだ。
現れた珍客に、京伝はどんな対応をしたのか。京伝の弟・京山が『蜘蛛の糸巻』で記録している。京伝はこんな言葉をかけたようだ。
「草双紙の執筆は、世の中をわたっていく仕事を持って、その傍らで気晴らしがてらに行うものです。今、名が知られている作者たちもみなそうです」
戯作で生活していこうなどと思うなと釘を刺しながら、誰かの弟子について習うものでもないと、こう続けている。
「戯作は、誰かの弟子になり教わることは一つもない。私もそうだし、今も昔も戯作者には、一人も師匠はいない。弟子入りはお断りしたい」
がっくりしたであろう馬琴を励ますように、京伝はこんな温かい言葉もかけた。
「しかし、気軽にいらっしゃい。できた作品があれば、見てあげることはできます」































無料会員登録はこちら
ログインはこちら