相続で一番揉めるのはどういった資産? 相続・贈与を考え始めるのは"定年前"が鉄則な理由
■暦年贈与
1年間(1月1日~12月31日)に1人の人が受け取った贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要になります。この非課税枠は、贈与される人(もらう人)一人あたりの金額です。父親から110万円、母親から110万円を同じ年にもらった場合、合計220万円となり、110万円を超える部分に贈与税がかかります。
【注意!】
2024年からルールが改正されました。亡くなる前7年以内(以前は3年以内)に行われた暦年贈与は、相続財産に加算されます。
亡くなる直前の駆け込み贈与では、相続税対策の効果が薄れる可能性がある点に注意が必要です。
■相続時精算課税制度
60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度です。この制度を利用するには、最初の贈与の翌年に税務署への届出が必要です。
2024年1月からは、年間110万円までの基礎控除が設けられました。この基礎控除を除き、贈与者1人につき累計2500万円までの特別控除枠の枠内であれば、贈与時には贈与税がかかりません。2500万円を超えた部分には20%の贈与税が発生します。
また、年間110万円までは申告不要で、毎年この控除を利用できます。ただし、この制度を選択すると暦年贈与へ戻すことはできないため、注意が必要です。
生前贈与の注意点 名義預金はNG!
よくある失敗が、「名義預金」です。子供や孫の名前で作った口座に親や祖父母が入金しているケースです。
口座の名義人がその存在を知らず、自由に使えない状態では、税務署は「生前贈与」と認めません。
贈与を成立させるためには、「あげた」「もらった」という双方の認識があり、もらった人が自由に使える状態になっていることが重要です。
預金通帳や印鑑は名義人本人が管理し、「贈与契約書」を必ず作成するなど、贈与の事実を明確にしておきましょう。
贈与契約書の作成は税務調査や相続でのトラブルを避けるために有効で、渡す側と受取側の双方で保管しましょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

![投資経験ゼロでも老後を豊かにできる! 定年5年前に読むお金の本[超入門]](https://m.media-amazon.com/images/I/51iadaEk+uL._SL500_.jpg)

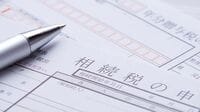




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら