1位沖縄、2位鹿児島、3位福岡…インフル流行地の意外な特性――感染拡大が冬だけじゃなくなった"根本原因"と"対処法"《医師が解説》
この研究では、冬季・夏季の気温が2.5~10℃上昇するシナリオを設定し、数値モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、気温の上昇はインフルエンザの季節性や流行パターンを大きく変化させる可能性が示された。
具体的には、冬の感染ピークが緩和される一方、春や秋にかけて相対的に感染が増加し、従来の「冬に集中する流行」から「年間を通じて分散した流行」へと移行する可能性が指摘されていた。日本でも新潟大学や長崎大学などの研究チームも、同様の研究結果を報告している。
いずれの研究でも、感染のピークは冬季では弱まり、ほかの季節へ分散するとしている。
一連の研究は、地球温暖化が感染症対策に新たな課題を突きつけていることを明らかにした。従来インフルエンザは「冬の感染症」として想定されてきたが、その前提を見直す時期に差しかかっているのだ。
これから行いたいインフル対策
では、どう備えたらいいか。
まず、インフルエンザは新型コロナと同じ呼吸器感染症であり、飛沫やエアロゾルを介して広がる。したがって、手洗い、マスク、換気といった基本的な感染対策の重要性は、両者に共通する。
今後、行っていきたい対策はワクチンで、インフルエンザ対策の中核である。我が国のインフルエンザワクチンは、南半球での流行を見ながら、A型とB型から2種類ずつ株を選んで、合計4種類の株から作成される。
今の流行を防ぐことはできないが、10月から接種が可能になるので、早めの接種を心がけたい。
インフルエンザワクチンの有用性については、数多くの論文が発表されている。
2023年に東京大学を中心とした研究チームが『ワクチン』誌に発表した、関東の自治体データを用いた8万3146人(65歳以上)を対象とした研究によれば、ワクチン接種群は非接種群に比べ、インフルエンザ発症のリスクが53%低下していた。
発症を予防する効果は接種したあと4~5カ月間持続し、その後は漸減する。特に高齢者では抗体が持続する期間が短いため、接種後数カ月を経過した症例では、ワクチン接種歴があっても感染・重症化のリスクを念頭におくべきだろう。
高齢者とならび、感染対策が重要なのは乳幼児だ。この年代では2回のワクチン接種が推奨されており、有用性は証明されている。
2021年に大阪市立大学を中心とした研究チームが発表した厚労省研究班報告によると、2018~2019年のシーズンでは、3歳未満の小児において、1回接種で83%、2回接種で58%感染リスクが低下していた。2019~2020年のシーズンでは1回接種で73%、2回接種で62%、感染リスクが低下していた。




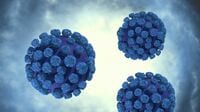


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら