1位沖縄、2位鹿児島、3位福岡…インフル流行地の意外な特性――感染拡大が冬だけじゃなくなった"根本原因"と"対処法"《医師が解説》
インフルエンザは、主に人の移動を介して世界中へと拡散される。その結果、北半球では主に冬、南半球では日本の夏にあたる時期に流行していた。そこが国内で散発的に小流行を繰り返す新型コロナや風疹、おたふく風邪とは大きく異なる。
人の往来が流行の成立に直結するため、水際対策はインフルエンザ抑制に効果的である。
その典型例が、2001年のアメリカ同時多発テロのあとの感染状況だろう。テロの後、航空機移動が大幅に制限された結果、その年はアメリカ国内でのインフルエンザ流行が確認されなかった。
また、新型コロナが流行した直後の2020〜2021年シーズンにも世界的なインフルエンザ流行が抑制された。これも国際的循環の遮断が大きく影響したと考えられている。
人の往来でウイルスが国内に
そもそも、インフルエンザウイルスは高温多湿に弱いと考えられているが、
そして近年、インフルエンザがもっぱら冬場に流行するという状況には変化が生じている背景には、グローバル化がある。
とりわけ注目したいのは、夏休み期間だ。この時期に多くの日本人が海外へ出かけ、同時に海外からも多数の旅行客が訪れる。その往来によってインフルエンザウイルスが国内に持ち込まれる。
思い返すと、2018年も夏にインフルエンザの流行があった。その要因として、夏休み期間中に海外旅行客が増加したことに加え、ラグビーワールドカップの日本開催により、夏から秋にかけてインフルエンザが流行する南半球との間で、人の往来が増えたことが影響したと考えられている。
今回、沖縄県をはじめとした外国人の受け入れが多い地域で、インフルエンザの感染が拡大したのも、このような事情を知れば納得がいく。
さらに、地球温暖化がインフルエンザの流行動態に与える影響も注目されている。今年2月に中国気象科学研究院の研究チームが、ネイチャー・パブリッシング・グループが発行する専門誌『Climate and Atmospheric Science』に発表した研究が興味深い。




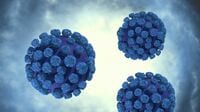


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら