夫が自宅のベッドで息を引き取った後、家に来て夫の死亡を確認したのは訪問医のS先生です。
S先生が初めて夫の診療にうちに来たのは2024年の2月6日。その10日後に夫は亡くなったので、ほんの短いお付き合いでしたが、痛み止めの使い方の指導などでお世話になりました。
「救急車を呼んではいけない」
夫が一度危篤状態になってから少し持ち直した時、S先生は私にこう言いました。
「次にまた危ない状態になったら、救急車じゃなくて僕を呼んでください」
もちろん、私はそのつもりでしたが、S先生は夫、そして私の意向をよく汲み取ってくれていたので確認の意味もあったと思います。
「救急車を呼ぶと、そのまま病院に連れて行かれて会えなくなってしまいます。さらに点滴などをして、長くつらい思いをさせてしまうこともあるから」
夫は延命処置を希望していませんでした。望んでいたのは、家で最期を迎えることです。
S先生は、心強い存在でした。うちの場合はいてくれたことで、在宅のままでも痛み止めの処方に困ることはなかったし、最期まで迷わなくてすみました。こちらの希望をしっかりわかってくれる、話を聞いてくれる方だったのが何より救いでした。
ただやっぱり、一番は家族、患者以外の誰かによるサポートです。
モルヒネ系の痛み止めは場合によっては少し意識を混濁させることもあるようで、夫も亡くなる数日前には話しているのに夢の中にいるような、朦朧としていたことが何度かありました。
発熱している時も同様で、眠っているわけではないのに意識がはっきりしないような状態の際に一人では、水を飲むことすら難しかったはずです。
自分の「その時」をサポートしてくれる人がいる人は、きっと幸せ者なのだと思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら





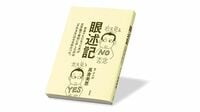


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら