5.6mmの極薄iPhone Airのみならず、iPhone 17シリーズが国や地域別にeSIM専用端末となり、物理SIMスロットを完全に排除した理由
それが、端末設計の自由度が増すということだ。方向性は2つある。1つは、これまで作れなかったような端末が作れるようになること。iPhone Airは、それに当たる。わずか5.6mmのiPhone Airは、内部のスペースを限界ギリギリまで切り詰めている。
基調講演で公開された内部画像を見れば、それは一目瞭然だ。端末のメイン基板はカメラ周りの出っ張った部分に格納されており、一見すると“本体”に見えるその下の部分には全面にバッテリーが敷き詰められている。みんなが本体だと思っていた部分のほとんどが、それを動かすためのエネルギーだったというのはなかなか衝撃的だ。

ここにSIMカードスロットを入れるとすると、どうなるのか。おそらくもっとも減らしやすいのは、バッテリーになるはずだ。一方で、バッテリーを減らしてしまうと、当然、電池の持ちにダイレクトに悪影響を与える。ユーザー体験を重視するアップルが、その方向に舵を切るとは考えづらい。
現に、iPhone Airは9月9日に発表された4製品の中で、唯一、自社設計のモデムである「C1X」チップを採用している。C1Xは、「iPhone 16e」に採用された「C1」チップを改良したもので、省電力性能に優れるのが特徴。C1比で性能は向上しているものの、ピーク性能で言えばまだまだその他のiPhone 17シリーズが採用したクアルコム製のモデムに軍配が上がる。
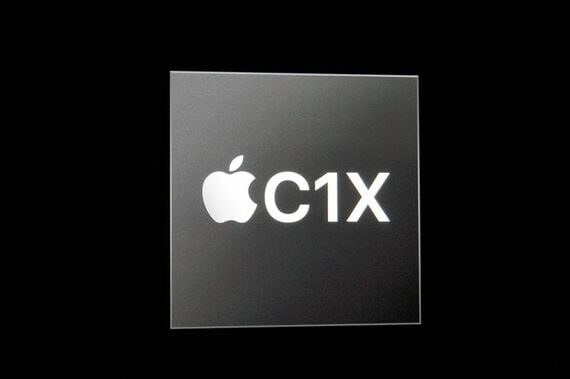
ギリギリのバッテリーしか搭載できないiPhone Airには、より電力効率の高いモデムしか採用できなかったと考えるのが自然だ。ギリギリまでバッテリーの容量を増やしてもなお、電力消費を減らさなければならなかったと言えるだろう。iPhone Airは、eSIMオンリーという選択肢が取れたからこそ実現できた端末というわけだ。
Proではバッテリーを増量、eSIM化の流れは進む
これに対し、eSIM専用化が“オプション”になっているiPhone 17シリーズは、SIMカードスロットを搭載しても、アップルが必要とする駆動時間の基準を十分満たせる。実際、iPhone 16シリーズまではSIMカードスロットを搭載していたが、iPhone 17シリーズはeSIM専用化を国や地域に応じて切り分けることにした。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら