"人生100年時代"を喜んでばかりはいられない…「昭和の親孝行」は、もはや"無理ゲー"という深刻
親が定めた人生を歩み、親の介護や面倒を見ることで自分の人生が大きく制約されることに対して、多くの人が疑問や抵抗を感じるようになっています。
「親が喜ぶから」、「親不孝と思われるから」という理由だけで、自分の人生を諦めたり、親の意向に逆らえなかったりすることは、子自身の精神的な苦痛や不満を増大させます。結果として、親への愛情が憎しみに変わり、「介護殺人」といった悲劇につながるケースさえ生まれています。
介護はもはや「個人の問題」ではない
⑤社会資源・インフラの発達と認識
昭和の時代、親の介護は家庭内で行われるのが主流であり、介護保険制度などの公的な社会資源は十分に整備されていませんでした。
1972年(昭和47年)に刊行された有吉佐和子のベストセラー『恍惚の人』(新潮社)は、まさに自力で介護を行わなければならなかった時代の産物です。
しかし、現在では、介護保険制度が導入され、さまざまな介護サービス(訪問介護、デイサービス、施設入居など)が利用できるようになりました。また、地域包括支援センターやケアマネジャーといった専門家が相談に乗ってくれる体制も整っています。
介護はもはや個人の問題ではなく、社会全体で支えるべき課題になっています。
社会資源を積極的に活用し、専門家の力を借りることは、現代の介護において不可欠であり、「期待に応える親孝行」モデルから脱却していく上で、極めて合理的な選択になっているのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

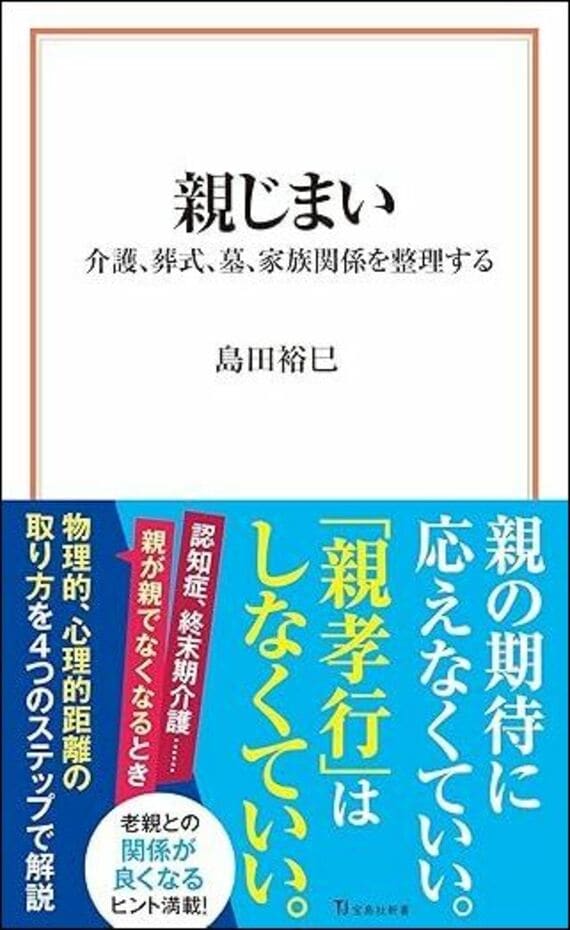
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら