【戦後80年】「シベリア抑留」終わらない戦後決算/死亡者の3割は未特定、経験者の平均年齢102歳で求められる解明の加速
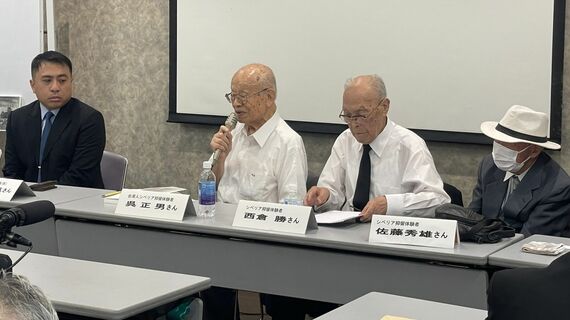
ソ連側は独ソ戦の激化で死者が全人口の1割超に当たる約2600万人に達し、深刻な労働力不足に直面。ドイツやオーストリア、ハンガリーなど枢軸国側の捕虜を労働に従事させており、日本人の抑留もこうした延長線上で極東の人員不足を補う目的で行われた。
シベリア抑留に詳しい関東学院大学の小林昭菜准教授は「スターリンの極秘指令では捕虜の受け入れを詳しく指示して抑留を行ったが、当初計画していた捕虜の規模は50万人。しかし実際には60万人以上を抑留することになり、食料や衣服、住居などの準備・整備が全く追い付いていなかった。結果、最初の冬である1945年~1946年にかけて死者全体の約8割が亡くなっている」と指摘する。
小林准教授によれば、ソ連側も死者の急増には対策の必要性を感じていたようで「部屋の温暖設備の充実や感染症抑制に向けたワクチン接種などがソ連内務省から出ていたが、地元住民の食糧確保すらままならない状況で物資が供給できる状態ではなかった」という。
こうした抑留に関する実態の解明に向けた取り組みは道半ばだ。
死亡者の正確な人数は不明
そもそも抑留された正確な人数の把握が難しい。所管する厚生労働省は帰還者などに聴取した調査の結果(同省社会・援護局 援護・業務課調査資料室調べ)として、抑留された人数は57.5万人、死亡した人数は5.5万人と推計する。
小林准教授によると、日ソ戦に関連した資料で捕虜の数は61万1237人となっているものの「抑留されるまでに亡くなったり、逃亡したりする人もいて、その中で実際に抑留された正確な人数はわかっていない。死亡者数もソ連に入った時の部隊別の人数がわかるだけで、抑留中は人によって収容所の移動などもあって追跡しきれない」という。
厚労省は死亡者数についてソ連・ロシア側から提供があった資料と日本側の資料で照会を進めており、今年9月5日時点で提供資料に記載された5万7050人のうち4万1149人が特定されている。現在も毎月10件程度のペースで名簿を更新している。
しかし、「ソ連側の資料では日本人の名前がカタカナで記録されているが、発音を聞き取れなかったのかまったく異なる名前になっていることもある」(同省援護・業務課調査資料室)ため、死亡者の特定には時間がかかっているという。ロシアがウクライナ侵攻を始めたことから、遺骨収集を含めた現地での調査も困難を極めている。
一方で、少しずつわかってきたこともある。




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら