ラーメンは常にトレンドが変化する。今提供しているものが5年後もウケているかはまったくわからない。その中で、「松屋」は「松太郎」というラーメン業態を独立店としてオープンするにあたり、まず看板メニューは誰にでも受け入れられる普遍的な醤油ラーメンにしようと考えたのだろう。
また、ラーメン業界が日々進化し、日常食からグルメ体験へと変化を遂げようとしている中、「松太郎」はあくまで日常食としてのラーメンを提供しようとした。
トレンドを追って商品開発をすると、この視点がブレてしまう可能性がある。「松太郎」のこのオーソドックスな商品展開にはその意思が見える。
現段階では、ラーメンファンの心をつかむのは難しい?

とはいえ、課題はある。「日高屋」「幸楽苑」と比べて一杯あたり200円ほど高い以上、顧客に「松太郎」を選ぶ理由を提示できなければならない。
もちろん、今後どんどんブラッシュアップされていくはずだが、現状のオーソドックスな味わいで、ラーメンファンの心を強くつかむのは難しいだろう。
また、カウンターのみの店舗設計は回転率向上には寄与するが、「ちょい飲み需要」を掘り起こすには不向きだ。「松屋」が牛めしに続く第二の柱としてラーメンを成長させるには、この方向性をどう整理するかが課題となる。
「吉野家」が「話題性」で、「すた丼」が「ブランド連想」で差別化を図ったのに対し、「松太郎」は「普通さ」で勝負に出た。「松屋」の挑戦は、ラーメン市場に「普遍性」という新たな競争軸を提示しているのかもしれない。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

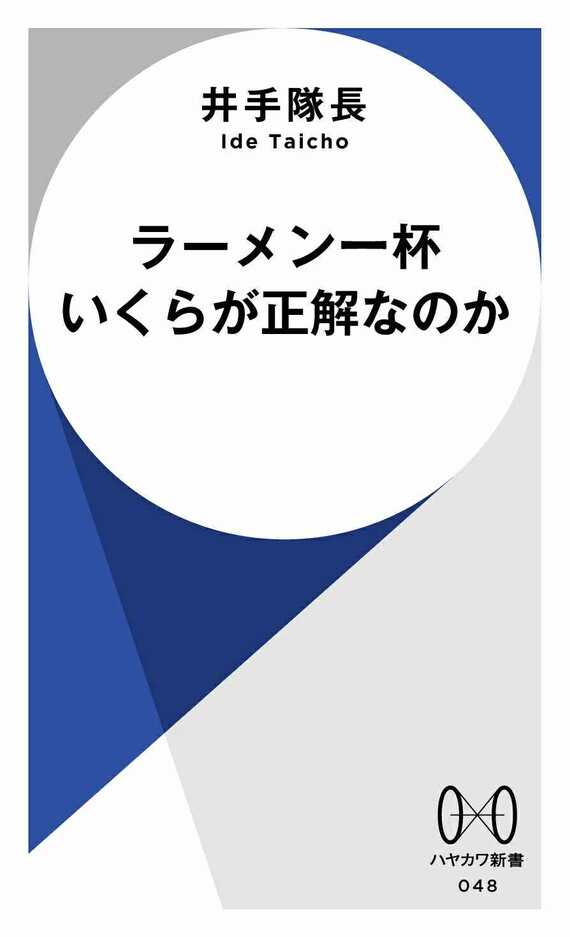






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら