しかし、「松太郎」の店内はカウンターのみ。しかも一席ごとに仕切りが設けられている。ラーメン専門店としては珍しい光景ではないが、ここから透けて見えるのは「客単価と回転率の両立」を意識した設計だ。
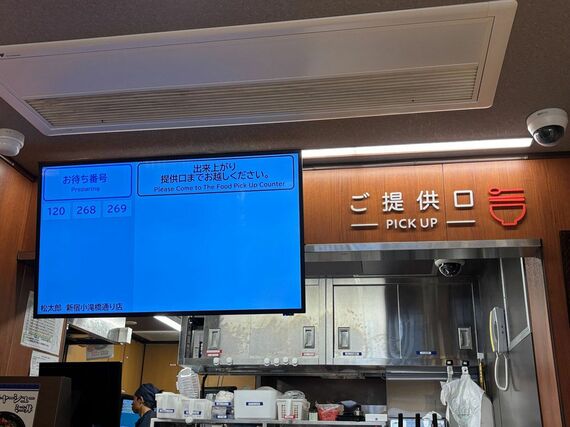
「ちょい飲み」需要も狙ってはいるものの、席の構成上、団体客やグループでの利用は難しい。むしろ一人客が短時間で食べて出ていくスタイルを前提にしている。これは「松屋」と同様の効率性を追求する姿勢であり、居酒屋的に「滞在時間で稼ぐ」発想とは一線を画す。
吉野家のラーメン注力とはどう違う?
ここ数年で、外食大手が次々とラーメンを主軸に据えたチェーン展開を始めている。

吉野家ホールディングスはラーメン店を「吉野家」「はなまるうどん」に次ぐ収益源に育てる方針を以前から掲げており、「ばり嗎」「せたが屋」「キラメキノトリ」など各ブランドを通じて展開を加速し、昨年5月にはラーメン店向けに麺やスープ、タレなどの商材を開発し、販売する京都の宝産業株式会社を子会社化し、万全の体制になっている。

今年7月4日からは「吉野家」で「牛玉スタミナまぜそば」を発売開始。「SNSで話題になるか」を第一義に考えた商品設計が特徴的で、マーケティング視点が強い商品だ。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら