「スマート洗面台」は、洗面台の鏡にカメラが内蔵され、住む人が毎日必ずそこに映す「顔」の情報を記録、蓄積できるというもので、近未来に定着するはずの健康デバイスのなかでも特に大きな期待が持てます。
目の前に座る患者さんの表情や肌の具合を観察し、顔が若干黒ずんでいるのであれば肝臓の異変を疑ってみる。これは人間の医師が実践していることです。
顔を毎日記録することで、その人の顔に微妙な変化が表れたらすぐに察知し、病気の可能性を検証して受診を促す。これはAIにとってまさに得意分野でしょうし、さらにまとめた情報をビッグデータとして集積できれば、間違いなくすばらしいアウトカムが得られるはずです。
顔情報が新たなバイオマーカーに
同じことはスマホでも可能になってくるでしょう。
1日1回、朝起きたときの表情をスマホで撮影し続けてある程度の枚数に達すると、その人の顔に普段と違うところがあったらすぐに病気との関連を調べ、健康状態を判定してくれるアプリに私たちの健康は見守られます。でも人によっては、ちょっと落ちつかないかもしれませんが……。
日々の顔情報の収集に大きな可能性を感じるのは、人間の顔の経年変化を可視化できるという点です。
日常のなかで、よく知っている人がある時期を境に急に老け込んだという印象を受けることはままあるでしょう。場合によっては、その人がしばらくして病気で亡くなったと知らせが入る、などということもあります。
しかし多くの場合、私たちは、全体の印象からなんとなくその人が「老けた」と感じるだけで、その人のどこがどう変わったのかを具体的に指摘し、言語化することはなかなかできません。
そうした「老け込み始め」の画像記録を100万人分、1000万人分と集め、AIに解析させれば、ある人の顔に表れた微妙な変化が、過去に肝硬変で亡くなった人たちとも共通する変化だった――そういうことがわかってくるのです。
実際に2023年以降、AIによる顔の表情や微細な変化の分析を通じて、心身の健康状態や特定の疾患の兆候を早期に検出する研究が活発化し、顔情報が新たなデジタルバイオマーカーとして注目されています。
これらの情報は、血圧や脈拍のようなウェアラブルデバイスで得られるデータよりも、はるかに有用性が高い情報になりえるのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

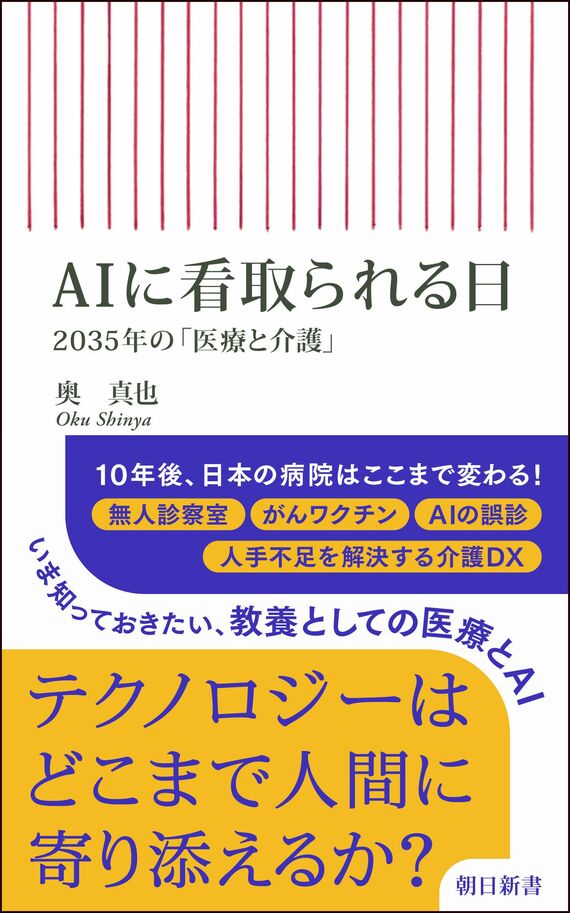































無料会員登録はこちら
ログインはこちら