当時の国際金融界のエリートたちは、ムッソリーニの独裁政権が労働組合を暴力的に弾圧し、賃金を強制的に引き下げる様を「秩序の回復」として歓迎し、積極的に金融支援を行った。
彼らにとって政治体制が自由主義か全体主義かなどは、二の次、三の次だったのだ。最も重要なのは、資本蓄積、つまりは自らの金儲けと蓄財に都合の良い経済秩序が維持されるかどうか、ただその一点だった。
ここに、現代を生きる私たちが得るべき最大の教訓がある。ある政策が打ち出され、ある政治的スローガンが叫ばれるとき、私たちは常に「それが誰の犠牲の上に成り立ち、誰に利益をもたらすものなのか」を問わなければならない。
通俗道徳が奪う「人間の尊厳」
本書が鋭く批判するのは、人々を巧みに支配し、服従させる言葉の力である。100年前のテクノクラートたちは、「勤勉」「節欲」「規律」といった個人の内面的な美徳を巧みに利用し、経済停滞の責任があたかも国民一人ひとりの倫理観の欠如にあるかのように罪悪感を抱かせ、緊縮策への抵抗を封じ込めた。
これは現代も同じ構図ではないだろうか。「痛みを伴う改革」「自己責任」「自助努力」――。これらの耳触りの良い、あるいは有無を言わさぬ言葉の裏で、誰かの犠牲の上に誰かの利益が築かれていないか。
私たちはその言葉が持つ暴力性とイデオロギー性を見抜く必要がある。
提唱者がいかに高名な学者や専門家であっても、その権威性に思考を委ねてはならないのだ。
著者のクララ・E・マッテイは、ファシストに抵抗し壮絶な死を遂げた大伯父に本書を捧げている。その献辞は、この本が単なる冷徹な学術書ではなく、人間の尊厳を取り戻すための闘いの一環として書かれたものであることを静かに、しかし力強く物語っている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




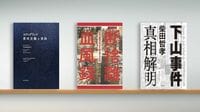


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら